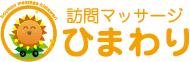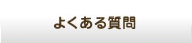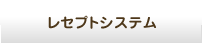お役立ち情報一覧

脳卒中などの後遺症による片麻痺により、麻痺側の筋緊張や関節拘縮が進みます。
リハビリをしないままでいると、拘縮が進み、可動域が狭くなってしまいます。
ですから、関節が固くなってしまう前に予防、また固くなった関節を柔らかくしていくことが大切です。
今回は、拘縮改善、予防の肘をまわすリハビリ方法を紹介したいと思います。
★肘をまわすリハビリ方法
本人様には仰向けに寝ていただきましょう。
介助者は本人様の麻痺側に座ります。
① 左手で本人様の手首を、右手で肘を下から支え、介助を行う人の膝上まで持ち上げます。
※麻痺側が右側の場合
② 手首を持っている手を内側にまわします。
③ 今度は反対に外側にまわします。
★注意点
無理にまわすと、筋肉や関節を痛める危険性があります。
できる範囲での運動にしましょう。
★ポイント
短い時間で毎日続けていくことが有効です。
リハビリは、本人さんが痛がらない範囲で、ゆっくりと、そして毎日行っていきましょう。

寝たきりの生活が多くなると拘縮が進み、可動域が狭くなっていきます。
関節が固くなってしまう前に予防、また固くなった関節を柔らかくしていくことが大切です。
脳梗塞の後遺症による片麻痺では、麻痺側の腕が曲がるように拘縮が進みます。
今回は、拘縮改善、予防の肘を伸ばすリハビリ方法を紹介したいと思います。
★肘を伸ばすリハビリ方法
本人様には仰向けに寝ていただきましょう。
介助者は本人様の麻痺側に座ります。
① 左手で本人様の手首を、右手で肘を下から支えます。
※麻痺側が右側の場合
② 肘をゆっくりと伸ばしていきます。
※拘縮が強い場合は、上腕の力こぶを揉みほぐしてから行いましょう。
★注意点
いきなり伸ばそうとすると、筋肉を痛める危険性がありまるので、ゆっくりと数を数えるペースで行ってください。
★ポイント
また、1度にたくさん行うと疲れがでたりしてよくありません。
それよりも短い時間で毎日続けていくことの方が有効です。
リハビリは、本人さんが痛がらない範囲で、ゆっくりと、そして毎日行うことがポイントになります。

寝たきりの生活が多くなると拘縮が進み、可動域が狭くなっていきます。
関節が固くなってしまう前に予防、また固くなった関節を柔らかくしていくことが大切です。
今回は、拘縮が弱い場合の肩のリハビリ方法を紹介したいと思います。
★拘縮が弱い場合の肩のリハビリ方法
<準備>
本人様には仰向けに寝ていただきましょう。
介助者は本人様の麻痺側に座ります。
① 左手で本人様の手首を、右手で脇を支えます。
※麻痺側が右側の場合
※※このとき、本人様の手のひらは必ず天井を向くようにします。
② 腕をゆっくりと大きく外へ広げていきます。
③ 腕を広げたところから、今度は腕を上げていきます。
★注意点
手のひらが床や介助者の方を向いていると、肩を動かした際、痛めてしまいますので、必ず手のひらは天井を向くようにしてください。
★ポイント
大きく動かしていきましょう。ただし、痛みがでればそれ以上は無理に動かさないようにしてください。
また、1度にたくさん行うと疲れがでたりしてよくありません。
それよりも短い時間で毎日続けていくことの方が有効です。
リハビリは、本人さんが痛がらない範囲で、ゆっくりと、そして毎日行うことがポイントになります。

寝たきりの生活が多くなると拘縮が進み、可動域が狭くなっていきます。
このように全身の関節は使わないとどんどん固くなっていきます。
固くなった関節を元に戻すことは大変です。
そうなる前の予防、また固くなった関節を柔らかくしていくことが大切です。
今回は、拘縮が強い場合の肩のリハビリ方法を紹介したいと思います。
★拘縮が強い場合の肩のリハビリ方法
本人様には仰向けに寝ていただきましょう。
介護者は本人様の麻痺側に座ります。
① 左手で本人様の肩を、右手で肘を下から支えます。
※麻痺側が右側の場合
② 腕をゆっくりと上に上げていき、上がるところまででやめます。
※介助者は手の力で上げるのではなく、自分の体重を利用して行う。
③ 腕を元の位置に戻し、今度は外に腕を広げます。
★注意点
不安定な関節で痛めやすいので、動かす際は、徐々に力を加えていきましょう。
★ポイント
ゆっくりと時間をかけて行っていきましょう。
また、1度にたくさん行うと疲れがでたりしてよくありません。
それよりも短い時間で毎日続けていくことの方が有効です。
リハビリは、本人さんが痛がらない範囲で、ゆっくりと、そして毎日行うことがポイントになります。

寝たきりの人の中には、膝が曲がり、股関節の拘縮が強く開きにくい方も見えます。
関節は使わないとどんどん固くなっていきます。
固くなった関節を元に戻すことは大変です。
そうなる前の予防、また固くなった関節を柔らかくしていくことが大切です。
今回は、拘縮が強い場合の股関節リハビリ方法を紹介したいと思います。
★拘縮が強い場合の股関節リハビリ方法
本人様には仰向けに寝ていただきましょう。
介護者は本人様の下肢側に座ります。
※介護者は本人様の両足を揃え、自分の足の間に入れます
自分の脚で本人様の脚を両側から挟むイメージです。
① 本人様の両膝の間にクッションを挟みます。
② 介護者は、右手を本人様の右膝の内側へ、左手を本人様の左側の内側におきます。
※介護者の手が交差する形になります。
③ 両手で膝を押していき、少しずつ膝を広げていきます。
★注意点
膝を広げる際、扉を開くように手を交差させない開き方をすると、
力が入りにくい上、力加減が難しいのでやめましょう。
★ポイントは、ゆっくりと時間をかけて行っていくことです。
固くなった関節を動かしますので、ある程度の痛みは伴うこともありますが、
痛みが出たら無理をしないようにしましょう。
また、1度にたくさん行うと疲れがでたりしてよくありません。
それよりも短い時間で毎日続けていくことの方が有効です。
リハビリは、本人さんが痛がらない範囲で、ゆっくりと、そして毎日行うことがポイントになります。

関節は使わないとどんどん固くなっていきます。
固くなった関節を元に戻すことは大変です。
そうなる前の予防、また固くなった関節を柔らかくしていくことが大切です。
今回は、介護者ができる肘のリハビリ方法を紹介したいと思います。
★肘のリハビリ方法
本人様には仰向けに寝ていただきましょう。
介護者は麻痺側に立ち、本人様と向かい合うようにします。
リハビリ1
① 本人様側の方の手で肘を支え、もう一方の手で手首を包むように持ちます。
② 手首を持っている手を内側へ回し、元に戻します。
リハビリ2
① 本人様側の方の手で肘を支え、もう一方の手で手首を持ちます。
② 肘を支えながら、手首を持っている手を押し、本人様の腕を曲げます。
③ 肘を支えながら、手首を持っている手を引き、本人様の腕を伸ばします。
十分に伸びたところで、元の位置に戻します。
★ポイントは、ゆっくりと時間をかけて行っていくことです。
固くなった関節を動かしますので、ある程度の痛みは伴うこともありますが、
痛みが出たら無理な曲げ、引っ張りはしないようにしましょう。
本人さんが痛がらない範囲で、ゆっくりと行うことがポイントですよ。

介護とはどんなことをいうのでしょうか?
そういった質問に対し、「なんでもやってあげること」、「面倒を全部見ること」が介護だと考える方もみえるかもしれません。
しかし、それは誤解です。
大切なことは、できることは自分でやってもらうことです。
では、なぜ自分でやってもらうことが大切なのでしょうか?
それは、できることをしなければ、いずれそれはできないものになってしまうからです。
これはすべての人に言えることですが、関節も筋力も使わないものはどんどん機能を失っていきます。
例えば、宇宙飛行士の人でも、地球にかえってくるときには、自力で立つことも難しくなります。
それは、無重力の宇宙では筋力を使わないため衰え、重力のある地球にかえってきたとき自分の体を支えるだけの筋力がなくなってしまうからです。
また、このように一度落ちた筋肉を元に戻すのは、何倍ものトレーニングが必要になります。
その状態が、動くことの少なくなったお年寄りの方にも起こるわけです。
そうならないためにも、自分でやってもらうことが大切なのですね。
その他にも、本人のなにかをしようという意欲が減り、「なんにもしなくてもいい」という無気力な状態になってしまいます。
自分でやってもらうことがリハビリになり、またADL(日常生活動作)が上がります。
自分でできることは「やってもらう」ということが介護の上でとても大切なことなのです。

お年寄りの方の中には体を動かさないで一日ほとんどの時間をベッドで過ごすという方も少なからず見えると思います。
人は体を使わないと使える機能がどんどん衰え、使えなくなってしまいます。
そのまま放っておくと寝たきりになってしまうこともあります。
お年寄りの方を寝たきりにさせないためにも、そのような働きかけをしていく必要があります。
寝たきり予防として、介護者が意識すべき点は以下のものがあります。
●本人の体の状態をよく知っておく
無理に動いたりしない方がいい場合もありますので、主治医と相談し、今の状態をしっかりと把握しておくことが大切です。
●動きやすい環境をつくる
普段何気なく生活している家でも、お年寄りの方にとっては危険がいっぱいです。
お年寄りの方が安心して動くことのできるような環境作りが大切です。
●できることはやってもらう
できることでもやらなければ、本当に出来なくなってしまいます。
できることは積極的にやってもらい、機能回復・維持をしていくことが大切です。
●ヘルパーやケアマネージャーに相談をする
身内にいろいろ言われても、素直に聞いてもらえないこともあります。
そういった場合は、ヘルパーさんやケアマネージャーさんに相談をしてみるといいでしょう。
いいアドバイスをいただけると思います。
寝たきりを防ぐためには、本人さんの意欲も必要ですが、それ以外にも介護者が意識していかなけらばならない部分もあります。
上記の注意事項をしっかりおさえておくといいでしょう。

お年寄りの方へ思いやりのある介護をしていくことが大切です。
お年寄りの方との接し方・介護で基本となることは、コミュニケーションです。
本人さんの意思、プライド、個性を尊重した接し方をしていきましょう。
今回は、お年寄りの接し方と介護についてのポイントを紹介します。
① あいさつをする
あいさつはコミュニケーションの基本です。朝や寝る前はあいさつをしましょう。
② 何かする前に「何を」するのかを話す
食事や髪の毛を洗うなどこれから何をするのかを伝えるようにしましょう。
③ 相手にわかりやすく説明する
簡潔・具体的に説明をするようにしましょう。
一度に多くのことを言わないように注意です。
④ 一言声をかける
急に触られたり、後ろから声をかけられるとびっくりするものです。
不安を与えないように一言声をかけるようにしましょう。
⑤ 声の大きさ、トーン、話すスピードを意識する。
相手に聞き取りやすい声の大きさ、ゆっくりとした速さで話すことが大切です。
⑥ 相手の話を否定しない。
どんな内容でも頭から否定をしないで、話をよく聞いてあげましょう。
思いやりのある介護でお年寄りの方が安心して生活できるようにしていきましょう。

高齢者の方では、高い音が聞きとりにくくなる、音は聞こえてもそれが言葉として聞き取れないということが多くなります。
これが「老人性難聴」です。
聞きとりにくくなることから聞き返すことが多くなってしまいます。
そのため、コミュニケーションを上手くとることができず、次第に話すことを避けるようになってしまう方も少なくありません。
コミュニケーションをとらなくなることで、周囲から孤立してしまい、認知症につながるケースもあります。
高齢者の方に難聴の症状が出てきた場合は、以下の対処をしてください。
①お医者さんに受診する。
難聴の症状を感じたら、早めにお医者さんに受診するようにしましょう。
②はっきりと発音して話す。
早口・こもった話方は、聞きとりにくいものです。
はっきりと発音して、少しゆっくり話すように心がけましょう。
③補聴器を使用する。
お医者さんで補聴器が必要と診断された場合は、補聴器の専門店でつくってもらいましょう。
補聴器は、ぴったりと本人さんに合うようにつくるためには調整が必要ですので、
合うものを作ってもらうために、しっかりとアフターケアを受けましょう。
「老人性難聴」に対して、きちんと対処していきましょうね。