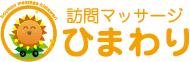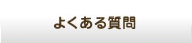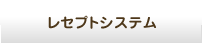お役立ち情報一覧
車椅子に適したクッション
車椅子のアイテムとして欠かせないのがクッションです。
クッションには、褥瘡の予防や座った姿勢を安定させるといった効果があります。
ただし、クッションならなんでもいいわけではありません。
良いクッションは、車椅子の座面と同じ四角形をしたものです。
このクッションなら、患者様が座ったとき体重を広い面で支えることができます。
逆に悪いクッションは、中心に丸い穴が空いているような円形のクッションです。
円形のクッションの場合、褥瘡予防のための除圧効果がほとんどないため、
クッションを敷く意味がなくなってしまいます。
また、クッションがずれやすく、ずれると座位が不安定になってしまいます。
車椅子のクッションには、四角形のクッションにしましょう。
クッションを使用すると、その分「前座高」や「背もたれの高さ」も変わりますので、
それも計算に入れて、高さを調節することも忘れないように。
布団から立ち上がり移動した場合、その後、今度は布団に戻る必要があります。
麻痺が強く、筋力が低下している人は介助が必要です。
今回は、片麻痺の方を椅子から布団へ戻す介助方法を紹介します。
☆片麻痺の方を椅子から布団に戻す介助
① 椅子から立ち上がらせる
介助者は、介助を受ける人の体を支え、声をかけながら立ち上がらせます。
立ち上がった後は、本人の腰に手をあてて腰を支えることで立位を安定させます。
② 体の向きを変える
椅子の正面に立つように体の向きを変えます。
しっかりと腰を支えて行いましょう。
介助を受ける人には、座っていた椅子に手をついてもらい、体のバランスが安定するようにしてもらいます。
③ 膝をつく
介助者は、自分の体勢を低くしていきながら、介助を受ける人に健側の膝を曲げてもらいます。
その後、患側の膝を曲げますが、膝が曲がりにくい場合は、介助者が曲げる手伝いをします。
④ 腰を下ろしてもらう
両膝が布団の上についたら、介助者は座位が安定するまで腰を支えます。
この介助でのポイントは、介助を受ける人を急がせないこと。
急いで行うと危険ですので、ゆっくりと行うようにしましょう。
麻痺が強く、筋力が低下している人は介助でベッドに寝かせます。
寝かせる介助は、上手に介助を受ける人の体を支えないと、体のバランスが崩れ、ベッドの柵などに頭を打ってしまうこともあります。
立ち上がりの時よりも、寝かせる時の方が事故が多いので慎重に行うようにしましょう。
今回は、片麻痺の方をベッドに寝かせる介助方法を紹介します。
☆片麻痺の方をベッドに寝かせる介助
① 座ってもらう位置に気をつける
まず、介助を受ける人にはベッドに座ってもらいますが、足元に近い位置に座っていると寝かせたときに頭が枕に届きません。
寝かせたとき、ちょうど枕の位置に頭がくるところに座ってもらいます。
② 肘をつかせる。
介助を受ける人の体を支えながら、本人にはベッドに肘をつかせます。
③ 体を倒していく
介助者は介助を受ける人の肩を抱いて体を支えながら、健側の肩からゆっくりと下ろしていきます。
④ 足をベッドにのせる
上半身をベッドに寝かせたら、介助を受ける人の膝の少し上あたりを持って両膝をベッドに上げます。
⑤ 体を仰向けにする
患側の肩を支えながら、ゆっくりと体を仰向けにします。
あわてず、ゆっくりと体の向きを変えながら寝かせるのがポイントです。
麻痺が強く、筋力が低下している人は介助による立ち上がりになります。
今回は、片麻痺の方が布団から椅子を使って立ち上がる介助方法を紹介します。
☆片麻痺の方が布団から立ち上がる介助
布団に座った状態でいるところからの説明です。
① 腰を支える
まず、介助を受ける人には椅子に健側の手をついてもらい、介助者は本人の腰を両手で支えます。
② 膝を立ててもらう。
介助を受ける人に膝を立ててもらい、介助者は後ろから腰を支えながら腰を浮かせます。
③ お尻を押す
腰を浮かせる際、腰が浮きやすいように介助者は後ろから膝で軽くお尻を押します。
周りに物などがあると危険ですので、普段からなにも置かないようにしましょう。
片麻痺の方が布団から立ち上がると聞くとなんだか大変そうに思いますが、
麻痺が軽く、ある程度の腹筋と腕力などがあれば自力で起き上がることが可能です。
今回は、片麻痺の方が布団から立ち上がる方法を紹介します。
☆片麻痺の方が布団から立ち上がる方法
布団に座った状態でいるところからの説明です。
① 麻痺側の脚を立てる
まず、四つん這いになり健側の手と膝で体を支えながら、麻痺側の脚を立たせます。
② 健側の脚を立てる。
健側の手で体を支えながら、今度は健側の脚を立てます。
※健側の脚がたったら、腰を浮かせましょう。
③ 体を起こす
腰の位置が安定したら、徐々に体重を足の方に移動させ、上体を起こします。
周りに物などがあると危険ですので、普段からなにも置かないようにしましょう。
今、布団で寝られているという方も少なくないと思います。
布団からの起き上がりですが、基本的にはベッドでの起き上がり方法と同じです。
しかし、腹筋の弱い人となるといきなり起き上がるのはとても大変です
今回は、腹筋の弱い人でも布団から楽に起き上がる方法を紹介します。
☆腹筋の弱い人が布団から起き上がる方法
① 布団にうつ伏せになる。
② 片方の膝を立てる。
一度軽く横向きになり、片方の膝を立てます。
③ もう一方の膝を立てる。
両方の肘で上半身を支え、もう一方の膝も立てます。
④ 四つん這いの姿勢になる。
布団に手をついて腕を伸ばし、四つん這いになります。
⑤ 腰をおろして座る
腰を下ろしながら体を回し、布団に座ります。
これなら腹筋の弱い人でも楽に起き上がることができます。
今、布団で寝られているという方も少なくないと思います。
布団からの起き上がりですが、基本的にはベッドでの起き上がり方法と同じです。
しかし、布団はベッドと違い、柵もありませんし、高さもないので、片麻痺の方は上手に体を使わなければ起き上がるのは大変です。
今回は、そんな布団から楽に起き上がる方法を紹介します。
☆片麻痺の方が布団から起き上がる方法
片麻痺の方が布団から起き上がる際は、患側の手をお腹の上にのせておきましょう。
① 頭を上げ、両膝を曲げる。
② 健側に横向きになる。
頭を上げ、膝を曲げたまま、健側に寝返ります。
③ 肘をついて上体を起こす。
肘をつき、ゆっくりと伸ばしながら体を起こします。
④ 手をつく
肘を伸ばし体を起こしたら、布団に手をついて体を安定させます。
腕の力と腹筋を主に使って起き上がるのがポイントです。
体の運動機能が低下していたり、脳梗塞の後遺症で片麻痺がある人がベッドから起き上がるのは大変です。
そういった場合には、ギャッジベッドを利用すると便利です。
ギャッジベッドとは、ベッドの上半分が自動(手動)で上下できるベッドのことで、これを利用するとより楽に起き上がりができます。
今回は、そのギャッジベッドを利用した起き上がりの方法を紹介します。
☆ギャッジベッドを利用した起き上がり方法
① 体を横に向ける
ベッドの柵を握り、両膝を立て、健側に倒すことで横向きになります。
② ベッドから足を下ろす
横向きになったら、両膝を伸ばし、ベッドの外に足を出します。
患側の足が下ろせない場合は、下になった健側の足で患側の足を持ち上げて下ろします。
③ ベッドを上げる
リモコンを使って、ベッドの背を上げます。
④ 体を起こす
柵を握り、ゆっくりと体を起こします。
ギャッジベッドは、買うと高いですが、便利ですし、レンタルもできますので使用されるととても楽になります。
体の運動機能が低下していたり、脳梗塞の後遺症で片麻痺がある人がベッドから起き上がるのは大変です。
楽に起き上がるには、ベッドの柵を使い、健側の腕力や体の回転・てこの力をうまく利用する必要があります。
今回は、自力でベッドから起き上がる方法を紹介します。
☆ベッドからの起き上がり方法
① 体を横に向ける
ベッドの柵を握り、両膝を立て、健側に倒すことで横向きになります。
② ベッドから足を下ろす
横向きになったら、両膝を伸ばし、ベッドの外に足を出します。
患側の足が下ろせない場合は、下になった健側の足で患側の足を持ち上げて下ろします。
③ 体を起こす
ベッドに健側の肘をつき、力を入れて体重を支えながら体を起こします。
両足をベッドから下ろす時の反動を利用して、上体を起こしてもOK。
④ 座る
柵を握っている手に力を入れて、バランスをとり座った姿勢を安定させます。
いきなり起きようとしても難しいですが、この方法なら少ない力で楽に起き上がることができます。
訪問マッサージひまわりでは一緒に働いていただける【マッサージ師】を募集しています。
ひまわりから独立された先生
ひまわりで働くメリットの一つ開業ノウハウが学べることがあります。
では、実際独立された先生がどうなったか?
川久保先生は、2年前にひまわりでいっしょに仕事をしていただきました。
岐阜まで鍼灸と訪問マッサージを学びにみえた勉強家でした。
鍼灸施術・東洋医学の知識が豊富でとても、勉強熱心な先生で、患者さま・利用者さまからの
信頼も厚く、おしまれて、ひまわりを卒業されたことを思い出されます。
現在は、神奈川県へもどり訪問マッサージを開業されてとても成功されています。
川久保診療所訪問マッサージ
卒業された先生のようにひまわりで、いっしょに顔晴っていただける方はこちら
● 開業ノウハウが学べる
● 多くの症例が学べる
● 事務実務が学べる
● レセプト業務が学べる
● インターネットを使った集客スキルが学べる