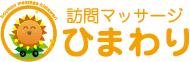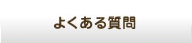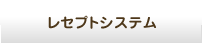お役立ち情報一覧
訪問マッサージひまわりでは一緒に働いていただける【マッサージ師】を募集しています。
多くの症例が学べる
ひまわりで学べることの一つとして、多くの症例が体験できるということがあります。
・ 脳梗塞後遺症
・ 脳出血後遺症
・ 関節リウマチ
・ 筋萎縮性側索硬化症
・ 脊柱管狭窄症
・ 脊髄損傷
・ 脊髄小脳変性症
・ パーキンソン病
・ レビー小体病
・ 悪性腫瘍など
多くの悩みを持っている患者さまが何にお困りなのかがよくわかるかと思います。
教科書で読んでわかること以外に、現場ではもっと多くの悩みがわかるようになります。
また、そこで悩みを解決する方法を考える必要になります。
ここで、いろいろな経験をもつベテランのスタッフの先生にアドバイスを聞くことで、
多くの知識を知恵に変えることできます。
そうして、多くの勉強・体験をつけることで、本当に悩まれている患者さまを笑顔にすることができるようになります。
多くを学び、いっしょに患者様を笑顔にしてみませんか(^^
訪問マッサージひまわりでは一緒に働いていただける【マッサージ師】を募集しています。
開業ノウハウが学べる
ひまわりで働くメリットの一つ開業ノウハウが学べることがあります。
訪問マッサージをいざはじめよう!と思っても学ぶべきことは多くあります。
施術・営業・経営・ネット戦略など。
なかなか0からはじめよう!と思ってもどこからはじめたらいいのかわかりません。
では、最近良く目にするノウハウ本を買えばいいのでしょうか?
それもいい方法です。
でも、実際の実務は本や冊子では伝えられないことが多くあります。
一言でいうと“イレギュラー”これは実際体験してみないとわかりません。
現場で困ることの多くは、誰でも捕れそうなフライやぼてぼてのゴロではなく、
教科書に書いていない “イレギュラー” な事例なんです。
この事例を多く体験できるかできないかで、いざ自分で始めたときに困ることが少なく
なります。
百聞は一見にしかず。
あなたも、ひまわりで、いろいろな経験をしてみませんか?
やる気がある方ならいつでも大歓迎。
一緒に患者さんを喜ばせていただける方には知識・理論・ノウハウは出し惜しみません。(^^
ひまわりで、いっしょに顔晴っていただける方はこちら
● 開業ノウハウが学べる
● 多くの症例が学べる
● 事務実務が学べる
● レセプト業務が学べる
● インターネットを使った集客スキルが学べる
暑さが和らいできたとはいえ、今年の夏は異常に暑かったですね。
この暑さで体調をくずされてみえた、Yさん。
病名は脳梗塞後遺症。室内は4点杖を使って歩行が可能でしたが、
この夏に調子をくずされてから、室内でも車椅子生活になっていました。
治療・リハビリの内容は、
● 全身のマッサージ
● 両脚の可動域訓練
● 鍼灸治療
週1回行っていたときは、それほど効果が実感できなかったご様子。
今月より、施術回数を週3回にしたところ、歩行も以前のようにもどってきました。
治療効果・リハビリの効果が感じられないときは、施術回数を増やすことも
いいかもしれません。
施術回数のご相談は、気軽にお電話、施術者にご相談ください。
ベッドで患者様を手前に移動させる介助方法【下半身の移動】
介助を受ける方の体の向きを変えるといった動作の前に、仰向けのまま横に移動させなけらばならない場合があります。
まず、この移動の場合には、無理に全身を動かそうとすると大変です。
ですから、上半身と下半身に分けて動かすようにしましょう。
その方が、スムーズに行えますし、患者様の負担も少なくて済みます。
今回は、まず、下半身の介助の方法を紹介します。
☆介助の方法
① 介助を受ける方の膝を立てる
膝を立ててもらうことで腰を浮かせやすいようにします。自力でできる方には自力で立ててもらいます。
② 腰を支える
片手を腰の下に、もう一方の手を膝の少し上に入れて腰と脚を支えるようにします。
③ 手前に移動させる
両手で支えた下半身を手前に引きます。介助を受ける人が重い方の場合は、ベッドに膝を刺させている側の足をのせ、腰を支えている側の足をベッドの側面に当てて引くと少ない力で手前に引くことができます。
ある程度自力でできる人では、できるところは自力で動かしてもらうようにすると介助が楽になります。
訪問マッサージひまわりでは一緒に働いていただける【マッサージ師】を募集しています。
● 開業ノウハウが学べる
● 多くの症例が学べる
● 事務実務が学べる
● レセプト業務が学べる
● インターネットを使った集客スキルが学べる
マッサージ技術スキルはもちろんですが、施術にはコミュニケーション技術もとても大切。
治療効果を上げられるマッサージ師は、このコミュニケーション能力がとても高いことが多いです。この技術は現場での経験でしかわかりませんし、伝わりません。
ひまわりではベテランのスタッフに同行して、マッサージ技術・コミュニケーションの仕方を学ぶ研修プログラムがあります。
技術アップ・コミュニケーション能力をアップさせたい方は
一人で行う枕方向に引き上げの介助
患者さんが重い場合や介助者が複数人いる場合は、二人で介助を行いましょう。
しかし、介助者がいないこともあると思います。
そういった場合は、介助を一人で行わなければなりません。
今回は、患者様が重い場合でも一人で移動介助する方法についてお話します。
☆介助の方法 1
① 引き上げる方法
患者様の枕側から両脇をもって身体を引き上げます。
☆介助の方法 2
② 押し上げる方法
患者様の足側から腰を持って浮かし、上に押し上げます。
力が弱い介助者には難しいかもしれませんが、コツをつかめば一人でも素早く移動させることができます。
患者様が重い方ほど腰を痛める可能性が高くなりますので、注意して行いましょう。
二人で行う枕方向に引き上げの介助
患者さんが重い場合や介助者が複数人いる場合は、二人で介助を行いましょう。
そうすることで患者さんも介助者も負担が少なく楽に介助ができます。
今回は、バスタオルを使った移動介助についてお話します。
☆介助の方法
① バスタオルを敷く
この介助ではバスタオルを使います。普段からバスタオルを敷いておくと便利だと思います。
② バスタオルの四隅を持つ
介助者はベッドの両サイドからタオルの端を持ちます。
③ 持ち上げて移動させる
二人でタイミングを合わせて持ち上げ、一気に上に移動させます。
このとき、勢いあまって患者さんの頭をベッドボードにぶつけないように注意しましょう。
安全な方法ですので、複数の介助者がいる場合には、この方法を行うようにしましょう。
自力で行う肩のリハビリ
今回は、自分でできる肩のリハビリ方法を一つ紹介します。
このリハビリは、寝ながら簡単に行えますので、負担が少なく効果も期待できます。
☆リハビリの方法
① 指を組む
仰向けに寝た状態で、体の上で両手の指を組みます。
※拘縮が強く、指が組めない場合は、麻痺側の手首を握ります。
② 組んだ手を上に上げる
指を組んだら、ゆっくりと上に上げていきます。痛みがでない程度で止めます。
※上げられるところまで上げるだけでも十分に効果はありますので無理はしないようにしましょう。
このリハビリは、一日2回、朝と夜に10回ほどを目安に行うようにするといいです。
できる範囲でリハビリを行うことがポイントです。
私の友人が、大阪で訪問マッサージをやっています。
ひまわりと同じように、家・施設でプロの鍼灸施術や、マッサージが保険で受けられます。
施術者もやさしくて良い先生ばかりのようです。
こだわりも多く、少しでも患者様の状態を良くしようと、日々施術技術を研鑽されているようです。
訪問リハビリ・マッサージを大阪で探されているのならば、訪問リハビリ鍼灸マッサージセンターを
お薦めいたします。
枕方向に引き上げる介助方法
今回は、患者さんが軽い方の場合の引き上げ介助の方法についてお話します。
一般的には、肩と腰に手を回し、患者様の体を少し持ち上げるようにしてシーツの上をすべらせるようにします。
☆介助の方法
① 患者様を抱える
片方の手を患者様の頭の後ろを通して肩を抱き、もう一方は下から腰を支えて、患者様の体を少し浮かせます。
② 枕の方にすべらせるように移動させる
腰を十分に下ろし、力を入れて枕方向にすべらせながら移動させます。
この時、腰が高いと痛める可能性がありますので、注意するようにしてください。