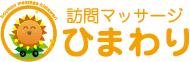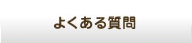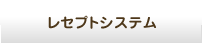お役立ち情報一覧
清拭は「顔 → 手・腕 → 胸部 → 腹部 → 背部 → 脚・足」の順番で行っていきます。
今回は「背部」の清拭の方法をお話します。
まず、背部の清拭を行うときは、お年寄りの方に横向きに寝てもらいます。
背部の清拭の際は、下半身はタオルケットでおおいながら行いましょう。
☆「背部」の清拭
背部を拭くときは、少し熱めの蒸しタオルを使用します。
① 腰から肩甲骨までを拭きます。
下(腰)から上(肩甲骨)へ外向きに円を描きながら大きく拭くのがポイントです。
② 背中の真ん中を拭きます。
背骨のラインは上下に大きく拭きます。
③ お尻を拭きます。
お尻を拭くときは、外側から内に円を描がくように拭いていきます。
④ 首元を拭きます。
首元から肩に向かって拭きます。
清拭は、マッサージの目的もありますので、拭く方向は原則として心臓に向かって拭くようにします。
蒸しタオルで拭いたところは、しっかり水気を拭き取ってください。
清拭は「顔 → 手・腕 → 胸部 → 腹部 → 背部 → 脚・足」の順番で行っていきます。
今回は「腹部」の清拭の方法をお話します。
まず、腹部の清拭を行うときは、お年寄りの方に仰向けでがで寝てもらいます。
腹部を除いての上半身と下半身はタオルケットでおおいながら行いましょう。
☆「腹部」の清拭
お腹を拭くときは、内臓を押さえつけないように拭くのがポイントです。
① おへその周りを拭きます。
※おへその周りを拭くときは、腸の走行に沿って「の」の字を描く様に時計回りに拭く様にしましょう。
② 横腹、股関節付近を拭きます。
※関節の境目は、汚れがたまりやすいので丁寧に拭きましょう。
清拭は、マッサージの目的もありますので、拭く方向は原則として心臓に向かって拭くようにします。
蒸しタオルで拭いたところは、しっかり水気を拭き取ってください。
脳の神経がなんらかの原因でうまく作用しなくておこる筋肉が思い通りうごかせなくなる症状をジストニアといいます。
原因が未解明であり、個々の症状の違いも大きいため、治療法がなかなか見つからない。
この症状に脚光があたっているのが、鍼灸治療。リハビリの一環として行われています。
5ミリほど皮下にさして、10分間程度おくという方法が多くつかわれます。
ある実験では患者32人(男性17人、女性15人、平均年齢40・8歳)を対象にしたものでも、副作用無く、自覚的症状の改善が見られたとされています。
ひまわりでも、このような症状に対しては、リハビリと鍼灸を併用する施術。マッサージとリハビリを併用した施術を行っています。
清拭は「顔 → 手・腕 → 胸部 → 腹部 → 背部 → 脚・足」の順番で行っていきます。
今回は「胸部」の清拭の方法をお話します。
まず、胸部の清拭を行う際はお年寄りの方に仰向けで寝てもらいます。
胸部を拭く際もタオルケットは肌から離さず拭く部分以外の場所にかけて行います。
☆「胸部」の清拭
① 首元は鎖骨に沿って外側に拭きます。
② 乳房は外側に向かって円を描くように拭きます。
※女性の場合は、乳房の下側に汚れがたまりやすいので丁寧に拭いてください。
③ 胸の中央は骨に沿ってお腹に向けて拭きます。
④ 横腹は上下にやさしく拭きます。
一度拭いたタオルの面で再度拭かないよう面をかえたり、タオルをかえて拭きましょう。
清拭は、マッサージの目的もありますので、拭く方 向は原則として心臓に向かって拭くようにします。
蒸しタオルで拭いたところは、しっかりと水気を拭き取ってください。
清拭は「顔 → 手・腕 → 胸部 → 腹部 → 背部 → 脚・足」の順番で行っていきます。
今回は「腕」の清拭の方法をお話します。
まず、上半身の清拭を行うときは、座位が保てるのならば座ってもらいます。
拭いている部分以外はタオルケットでおおいながら行いましょう。
☆「腕」の清拭
① 手のひら、指を拭きます。
※指の間などは汚れがたまりやすいので念入りに拭くようにしましょう。
② 手から肩に向けて腕を拭きます。
※反対側も同じように行いますが、一度拭いたタオルの面で再度拭かないよう面をかえたりタオルをかえて拭くようにしましょう。
③ 手を上げて脇の下を拭きます。
清拭は、マッサージの目的もありますので、拭く方向は原則として心臓に向かって拭くようにします。
蒸しタオルで拭いたところは、乾いたタオルでしっかりと水気を拭き取ってください。
清拭は「顔 → 手・腕 → 胸部 → 腹部 → 背部 → 脚・足」の順番で行っていきます。
今回は「顔」の清拭の方法をお話します。
まず、上半身の清拭を行うときは、座位が保てるのならば座ってもらいます。
拭いている部分以外はタオルケットでおおいながら行いましょう。
☆「顔」の清拭
① 目頭から目尻に向けてやさしく拭きます。
※反対側も同じように行いますが、一度拭いたタオルの面で再度拭かないよう面をかえて拭きましょう。
② 額 → 頬 → アゴ の順で、鼻の下で交差するようにS字に拭きます。
③ 目ヤニを取ります。
※目ヤニは無理にとらないで、常用の目薬などで目ヤニをやわらかくしてから拭き取ります。
④ 鼻・耳を拭きます。※耳の後ろやつけ根も丁寧に拭いてください。
清拭は、マッサージの目的もありますので、拭く方向は原則として心臓に向かって拭きましょう。
蒸しタオルで拭いたところは、しっかり水気を拭き取ってください。
清拭とは、濡れたタオルなどで体を拭いてきれいにすることをいいます。
清拭を行うには「蒸しタオル」が必要です。
今回は、その蒸しタオルの作り方を紹介します。
☆蒸しタオルの作り方
①タオルをお湯で温めて作る方法
用意 ・55℃くらいのお湯を溜めた洗面器を用意します。
・厚手のゴム手袋
厚手のゴム手袋を着用し、タオルをお湯につけてからしっかりしぼります。
※このとき、やけどをしないように注意してください。
②電子レンジを利用して作る方法
用意 ・水かお湯でしぼったタオル
・ビニール袋
水・お湯でしぼったタオルをビニール袋に入れ、3分ほど電子レンジにかけます。
せっかく温めた蒸しタオルも時間が経過すると冷めてしまいます。
冷めにくくする工夫として、温めたタオルは、発砲スチロールの箱に入れたり、厚いビニール袋・数枚重ねたビニール袋の中に入れておくようにしましょう。
清拭とは、濡れたタオルなどで体を拭いてきれいにすることをいいます。
清拭は、お年寄りの方の体調を見て行うようにします。
清拭は疲れるので、お年寄りの方の負担にならないように、一日ずつ部位をかえて行う方法もいいでしょう。※「今日は手」「明日は足」など。
☆清拭を行う際の注意点
①体調を確認する
熱があるとき、気分が悪いときは中止します。
②トイレは済ませておく
途中で中断することがないようにトイレは済ませておきます。
③食事の前後1時間は避ける
空腹時・満腹時は体調が変化しやすいので清拭は行わないでください。
④本人ができるところはやってもらう
自分でやってもらうことでリハビリにもなります。急がせたりせず、ゆっくりと見守りましょう。最後に拭き残しがないかをチェックします。
⑤手を温めておく
手が冷たいとびっくりしてしまいます。介助を行う人は手を温めておきます。
⑥室温に気をつける
肌寒く感じる室温はよくありません。部屋の温度は23~25℃くらいに温めておきましょう。冬場は特に注意が必要です。
⑦プライバシーを保護する
カーテンを引いたり、拭く部分以外はタオルケットなどで覆うなどの気配りをしましょう。
清拭とは、濡れたタオルなどで体を拭いてきれいにすることをいいます。
まず、清拭で使用する蒸しタオルは温かいものを用意します。
冷たいものだと、お年寄りの方も気持ち良くありません。
しかし、熱すぎるものはヤケドの危険がありますので、介助者は必ず自分で触って温度を確認するようにしましょう。
蒸しタオルは冷めないように、発砲スチロールの箱に入れふたをしたり、ビニール袋を数枚重ねたものに入れておくといいです。
蒸しタオルは、3~4枚用意してください。
蒸しタオルで拭いた後にその部分の水気を拭き取るため、乾いたバスタオルも2~3枚用意してください。
また、お年寄りの方が裸のままでいないで済むようにあらかじめ着替えは準備しておきましょう。
☆準備するもの まとめ
・蒸しタオル 3~4枚
・バスタオル 2~3枚
・着替え
まず、清拭とは、濡れたタオルなどで体を拭いてきれいにすることをいいます。
・介助を受ける人の体調や障害によって入浴ができない場合
・入浴と入浴の間隔が長い場合
に行います。
清拭は、入浴と同様の効果があります。
☆清拭の効果
①感染の予防
体を清潔に保つことで、皮膚からの細菌感染を防ぐことができます。
②血行促進
マッサージ効果により、血液の循環が改善し、褥瘡の予防につながります。
③拘縮予防
手足を動かすことにより、関節の拘縮を防げます。
④皮膚のチェック
全身の皮膚観察ができるので、褥瘡などの異常を早期発見できます。
⑤気分転換
介助者とのコミュニケーションや清潔になった爽快感が介助を受ける人の生きる意欲になります。