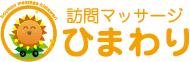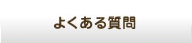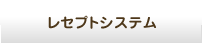お役立ち情報一覧
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回は脳梗塞後遺症で半身不随の歩行困難な60代前半の利用者様の施術に同行しました。
言葉はハキハキ話されます。まだお若いので、この歩けない状態がつらいそうです。
脳梗塞は年齢に関係なく起こる!?
推定患者数約92万人で、うち年間7万人が死亡すると言われているのが脳梗塞です。
脳梗塞は加齢を重ねていくことで発症率も上がっていきますが、最近では45歳以下で脳梗塞を発症する「若年性脳梗塞」も増加してきています。
高齢者の脳梗塞の原因で多い危険因子として下記のものがあげられます。
・加齢
・喫煙
・高血圧
・糖尿病
・脂質異常症
特に加齢や高血圧は脳梗塞の原因の中でも、多くの割合を占めています。
若年性脳梗塞では、血管が裂けてしまう動脈解離や、心臓の血栓(血の塊)がはがれて脳までいってしまう、膠原病などの自己免疫疾患が原因となることが多くあり、高齢者の脳梗塞の原因とは異なりることがあります。
脳梗塞の前兆
脳梗塞の前兆として、顔面神経麻痺、言語障害、感覚障害などの症状が現れます。
例えば・・・
・顔や手足が片側しか動かせなくなる
・呂律が回らなくなる(うまく喋れない)
・口がきちんと閉まらない(ヨダレを垂らしてしまう)
・めまいや立ちくらみが起こる
・目の焦点が合わない
・障害物がないところでもよくつまずく
施術の様子
マッサージ中は日常的な会話で先生と話したり笑ったりされて楽しそうに施術を受けてみえます。
側臥位での四肢のマッサージとROM訓練をおこないました。
寒いと動きが鈍くなるので、どうしても関節など硬くなりがちになってしまいます。
マッサージ開始時は少し痛がっていらっしゃいましたが、徐々に筋肉や関節が柔らかくなってくると、利用者様の表情も徐々にほぐれてきました。

ご家族様は「まだ若いから、早く杖で歩けるようになってほしい。」と願っていらっしゃいました。ご本人様も強く望んでみえました。
今後も「杖をついて歩けるようになる。」という目標に向かって、わたし達と一緒にがんばっていきましょう!
その他にも、こんなお喜びの声もとどいています!
わたし達は、利用者様の笑顔のために全力でサポートさせていただきます!
高齢者のほとんどは「骨粗鬆症」になっており、それが原因で骨折しやすくなっています。
骨粗鬆症とは、骨がもろくなり、骨折しやすい状態になる病気のことです。
高齢者の骨折は、若い人の骨折と違い、後遺症が残りやすく、その後の日常生活に支障をきたすことも少なくありません。
また、寝たきりになる原因でもあり、第一位の「脳卒中」に次いで「骨粗鬆症」は第二位となっています。
骨粗鬆症でなぜ寝たきりになるのかというと、骨折を治療するため安静にしなければならないので、その間に全身の筋力が落ち、寝たきりになってしまうからです。
しかし、骨折をしても必ずしも寝たきりになるわけではありません。「きちんとした治療とリハビリ」を行うこと。また、本人と家族の前向きな気持ちがあれば骨折したとしても寝たきりになる確率をぐっと下げることができます。
あきらめないで、治療とリハビリを続けていくことが大切です。
でも、まずは、骨粗鬆症の予防をし、骨折をしないことが大切ですね。
骨粗鬆症の予防としては、運動することがあげられます。
なぜなら、運動をすることで、骨は刺激を受け丈夫になるからです。
具体的な運動の方法としては「散歩」をおすすめします。
1日30分、距離にして約2キロメートルを毎日歩くようにしましょう。
毎日続けることで、骨は確実に丈夫になっていきますよ。
高齢者の骨折の特徴
一般健常者が骨折してしまったときには、交通事故などの強い外力を受けて周りの筋肉が傷ついたり、折れた骨が大きくずれたりすることにより、患部の強い痛みや腫れにより骨折した部位がはっきりわかるような症状が現れます。
しかし、高齢者の場合は違います!
わずかな外力でも骨折してしまうため、骨折した部分がズレることが少ないことも多く、骨折部の症状が軽度のために、受傷直後は強い痛みを感じないことも多くあるのです。
そのため骨折していることに気付かないまま、いつも通り生活し、骨折部のズレが大きくなってから病院にかかることも多いため、診断や治療が遅れることも少なくありません。
骨折しないためには
お年寄りの方が骨折する原因の約8割が転倒によるものです。
転倒するきっかけとしては、つまずいたり、滑るなどがあります。
例えば、敷居の段差や布団、座布団につまずいたり、床に置いてあった新聞・広告・チラシやお風呂場などですべったりがあります。

まず、そうならないためにも自宅では段差や障害物をなくすことが大切です。
また、お年寄りの方は加齢によって足腰が弱り始めているので、歩いたり、またいだり、登るために足腰を鍛えることも必要になります。
太ももの筋肉(大腿四頭筋)を鍛えることで、膝が安定し、階段などの移動が楽になります。
また、ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)を鍛えることによって、つまずきにくくなります。
「散歩」は毎日続けることで、筋肉を鍛えられるだけでなく、お年寄りの方に多い骨粗鬆症の予防にもなります。
このように転倒で骨折しないように予防をしていくことが大切です。
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回施術に同行させていただいた利用者様は、足の筋力が低下し、関節が硬くなってしまった方です。
仰臥位にて四肢のマッサージをおこないました。
今回は、首から腰にかけて痛みがあるとの事でしたので、頸部から腰にかけて指圧とさするようなマッサージの軽擦法でマッサージを念入りにおこないました。

ROM訓練ではご家族の方が、一つ一つの動作に喜んで下さっていました。
利用者様ご本人も、時折笑顔を見せながら、先生のかけ声にあわせて、ゆっくりと頑張っていらっしゃいました。
マッサージの体験の時から、とても気持ちがいいし楽になると好評をいただいていました。
マッサージを終えるころには顔の血色が良くなり、ご家族の方も喜んでいらっしゃいました。
「次回はいつ来てくれるの?」と先生に聞いていらっしゃいました。
楽しみにしていただけるというのは、とても嬉しい事ですね!
ROM訓練とは
ROM訓練とは、関節可動域の維持および増大を目的としておこなう他動的ROM訓練と、筋力の増強等を目的としておこなう自動介助的ROM訓練の二つに分があります。
自動的ROM訓練とは、患者さんが自分の力で行なう訓練で、他動的ROM訓練とは施術者が患者さんの体を動かして行なう訓練です。
ROMとは
ROMとは、Range of motionの略です。これは「関節可動域」という意味となります。
身体に障害が起こった場合や、また寝たきりになった場合、関節の動く範囲が狭くなり、関節可動域(ROM)が制限されてしまいます。
主な原因は、関節の拘縮や、骨の病変、寝たきりによる運動不足などにあります。なかには、外傷や筋の麻痺などで起こる場合もあります。
関節が拘縮することにより日常生活動作に障害をきたしてしまいます。
ROM訓練を行うことで、関節の拘縮を予防・改善できるため、患者さんの日常生活での自立を促すことができるのです。
寝たきりなどによる関節の拘縮でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回は、脳梗塞後遺症により左半身麻痺の利用者様の施術に同行しました。
左上下肢に軽度の拘縮がみられます。
リハビリとして歩行訓練をおこなっているようで、早く休憩したいからとゆっくり歩行しないで速いペースで歩行しているそうです。

そのため、お体に負担がかかってしまい痛みとして出てきてしまったようです。
右半身は、麻痺している左半身をかばう為、筋緊張がみられました。
施術の様子
ベッドにて、両側臥位で首から下肢にかけての<マッサージ、仰臥位で四肢のマッサージと関節可動域訓練をおこなます。
ご家族さまから、「マッサージをした夜はぐっすり眠てます。とても助かります。」とお喜びの言葉もいただけました。
他にもこんなお喜びの声がとどいています!
ぐっすり眠れるようになると、お身体だけでなく気分までスッキリしますね!
なかなか夜眠れないとお悩みの方、一度訪問マッサージを体験してみませんか?
わたし達が全力でサポートいたします!
随時無料体験もおこなっているので、お気軽にお問い合わせください。
安全な歩行をするために
歩行訓練をされている方の多くが、「早く元のように歩かなければ」と思いがちです。
確かに「元のように歩く」という気持ちは、訓練に対するモチベーションを上げるためにも効果を発揮します。
ですが、歩行訓練全てが「元のように歩く」ことが目的ではありません。
歩行訓練を初めて開始するときは「最初から元のように歩く事を目標にせず、まずは立ち上がって、バランスを保って身体を移動する(歩く)」訓練と考えるのほうが良いかもしれません。
数歩でもバランスを崩さずに身体を動かす(歩く)ことができれば、歩行訓練の第一段階の目標を達成したことになります。
歩行訓練とは、「前回よりもここまで〇〇ができるようになった」ということに重点をおいたほうがモチベーションも上がりやすくなります。
例えば、「前回よりも数歩多く歩けた」「前回よりバランスを崩さず歩けた」といった感じです。
訓練受ける方には「歩行訓練をしなければいけない」という義務感から疲れてしまったり、うまく成果があがらず訓練が嫌になってしまったりすることがあります。また、痛みがあるのに無理をして歩行練習を続けてしますことも少なくありません。
訓練は義務ではありません。体調を考慮しながら、無理のない程度で行いましょう。
こんにちは。コーディネーターの片田です。
 今回は、以前にベッドから落ちてしまい、体のあちこちを痛めてしまった利用者様のお宅を訪問しました。
今回は、以前にベッドから落ちてしまい、体のあちこちを痛めてしまった利用者様のお宅を訪問しました。
先生の事を本当に信頼されており、以前よりたくさん会話をしていただけるようになりました。
下肢の浮腫は左下肢は先週より浮腫は和らいでいましたが、右下肢はまだ浮腫は強めでした。
「今日は足が特に痛いから・・・。」と言われ、屈伸運動を中止し、変わりにこわばった筋肉をほぐすマッサージに変更しました。
さするようなマッサージの軽擦法がお好きなようです。
最近は笑ってくれます。私にも慣れてくれたみたいで、先生と三人で楽しく会話をしたりしました。
このように会話をすることにより、利用者様のお身体の状態をさらに知ることができます。
利用者様と先生の信頼関係とは、とても大切なものなのですね!
マッサージがもたらす効果
1、麻痺の改善
長期間麻痺した筋肉は、次第に筋力が低下していきます。マッサージにより血行を改善することで筋肉の残存能力が改善します。
2、筋力の維持・増加
高齢者の多くが寝たきりにより筋力が低下します。マッサージにより筋力低下の予防、日常生活動作の維持が図れます。
3、浮腫の改善
マッサージにより体内の水分・血液循環等を改善させ、浮腫を改善します。
4、関節の拘縮予防及び改善
寝たきりなどが原因で筋肉や関節が硬くなってしまう場合が多くあります。マッサージにより筋肉や関節を柔らかくすることができます。
5、褥瘡の予防・改善
寝たきりなどで長時間同じ姿勢が続くと、ベッドや椅子に接触している部分の血行が悪くなり褥瘡が起こりやすくなります。マッサージにより血行を促進し、褥瘡の予防・改善ができます
6、精神的不安の解消
マッサージによるスキンシップや、施術者とのコミュニケーションなどを通じ利用者様との信頼関係を築くことにより、精神的不安も解消され、心理的鎮痛効果も期待できます。
マッサージにはこのような効果が数多くあります。
訪問マッサージひまわりでは無料体験もおこなっているのでお気軽にお相談ください!
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回は、脳梗塞後遺症による麻痺の利用者様の施術に同行しました。
訪問マッサージを受ける前は、いつも寝ている事が多かったとのです。
下肢の筋力もかなり低下しており、立ち上がりが困難な状況でした。
高齢者の場合、転倒を恐れるあまりベッドや車いすから移動する機会が減り、寝たきりになられることが多いのです。
なぜ高齢者は転倒しやすいのか?
高齢者の転倒の原因は大きく分けて3つあります。
1、老化や脳梗塞などの後遺症による下肢筋力の低下
高齢者は病気やけがなどが原因で寝たきりになることが多くあります。
そのため下肢の筋力不足により、歩行時につま先を上げる動作がしづらくなります。
また、つま先が上らないため、すり足歩行になりつまずきやすくなるのです。
2、バランス感覚の低下
加齢に伴い、筋力の低下とともに平衡感覚(バランス感覚)をつかさどる器官が衰えていきます。
そのため、歩行の際に片足立ちになるとバランスが悪くなり、歩行動作が不安定になり、転倒してしまいます。
3、視力低下による段差などの認識不足
加齢に伴い、視力が低下することが多くあります。
すると、段差や周囲の物などに気が付きにくくなり、普段はなんてことないちょっとした段差でも、つまずき転倒しやすくなります。
施術の様子
訪問マッサージを受けるようになり、少しずつ足の筋力運動により筋力が回復傾向にあります。
マッサージとROM訓練の最後に、先生が横に付き添いながら立ち上がりのトレーニングをします。
随分立ち上がりが早くなり、背中が曲がり気味だった姿勢もだいぶ伸びていました。
ご家族様より「立ち上がることが楽になったからか、起き上がることが多くなりました。」とすごく喜んでいただけました。
他にもこんな声が届いていています!
今後はご自身の力でお散歩に出かけられるようにするために一緒にがんばっていきましょう!
わたし達が全力でサポートいたします!
※写真はイメージです。
●定期的なお通じがない。不規則
●浣腸してもなかなか出てくれない
●コロコロなど少ししかでない
●いつもお腹が張ってすっきりしない
●出ないから本人さんもイライラしている
便秘で悩んでみえる方も少なくないのではないでしょうか?
寝たきりの方や体を動かす機会が少ない方は便秘になりがちです。
訪問マッサージひまわりでは、便秘の方に対して、便秘解消・予防を目的としたお腹のマッサージも行っております。

訪問マッサージひまわりが行っているお腹のマッサージは、腸の蠕動運動を促す効果だけでなく、固くなってでにくくなった便の固まりをほぐして出やすくするため、便秘解消にとても有効です。
写真の方は、長い間便秘に悩まされてみえた方です。

マッサージを利用し始めてからは、定期的にお通じがあるようになり、本人さんのストレスもなくなったため、笑顔が増えました。
「お腹の張りがすっきりするようになったよ」とお喜びの声もいただいております。
マッサージ以外にも、体を動かすリハビリも行っておりますので、寝たきりなどの理由で運動不足からくる便秘症状の方も対応しております。
便秘症状でお悩みでしたら、一度訪問マッサージひまわりへご相談くださいませ!
無料体験も随時実施中です!
★こんな方には無料体験がおススメ!
●リハビリマッサージなどのサービスを受けようか悩んでいる
●本人様に少しでも楽になってもらいたい
●お身体の状態を少しでも変えたい
●マッサージについて知りたい
その他、ご不明な点、ご質問などございましたらお気軽にご相談くださいませ。
058-234-1386
自宅で簡単!お腹のマッサージ!
便秘のときには、お腹のマッサージをすると良いと言われています。
方法としては、おへそを中心に、右下腹部に両手を重ねて置き、そこから時計回りに下腹部までゆっくりと圧迫しながら手を移動させていきます。
ポイントとしては、お腹の力を抜いて、大腸に沿って押していくようなイメージでおこなうと効果的です。
お腹が張っているように感じる時や、就寝前、便座に腰掛けた時などにマッサージをすると排便を効率よく促してくれます。
また、マッサージと併用して温罨法も有効です。
温罨法とは、人の体、特に患部を温めることで新陳代謝を活性化させ、症状を緩和させるという治療法です。
蒸したタオルやカイロを腰やお腹に当てて、腸を温めるとリラックスもできるためおススメです。
一度お試しくださいね!
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回は脳出血後遺症で左半身マヒが残る利用者様の施術に同行しました。

四肢のマッサージと関節可動域訓練で筋肉と関節を柔らかくほぐします。
さらに下肢の筋力抵抗運動で足の力を付けるための筋力強化訓練をおこなました。
「歩けるようになりたいから、毎日足に声をかけてるのよ」と利用者様が話して下さいました。
“頑張れ” “歩ける”など、声掛けしているそうです。
「今では10歩くらい歩けるようになったわ」とお喜びの声をいただきました。
以前はほとんど歩くことができず、ベッドの上で過ごす日が多かったようです。
他にもこんな声が届いています!
「もっと歩けるように体力をつけてなきゃね」と意気込みいっぱいの利用者様。
お出かけが出来るようになるために、一緒にがんばっていきましょう!
わたし達が全力でサポートしていきます!
なぜ訓練が重要となるのか?
1、起立着席の繰り返しの訓練や歩行訓練などの下肢訓練の量を多くすることはで、歩行能力の改善が望める
2、訓練で同じ動作を繰り返しおこなうことで運動を再度学習しやすくなるから
3、単純に下肢の筋トレをおこなうのではなく、歩行訓練をおこなうことで歩行の筋収縮に近い状況でトレーニングができるため、より効果が望める
どれだけ歩くといいのか?
筋力の維持や筋肉の萎縮防止のために、ある程度の歩行量が重要であるという報告は多いです。
ある報告では、一般の中高年の方では、日常生活で1日4000歩未満しか歩いていない場合、麻痺などの運動障害がなくても筋力が低下すると言われています。
歩行をおこなうためには、筋力も重要となるため、麻痺などがある患者さんの場合でも、筋力低下を防ぐためには一日最低でも4000歩は歩いたほうが良いということになりますね。
麻痺がある場合の注意点
麻痺のある側の足は不安定で、骨折などを引き起こしやすいという特徴があります。これに加えて、麻痺のない側の足に体重をかけ過ぎて、不自然な姿勢をとりやすいのです。
立てるようになったら、まずはバランスを保つ練習を積極的にするようにしましょう。
また、歩く練習を行う前に、まっすぐに立てるか、足がではないか、手を離して立てるか、身体を回転させてバランスがとれるか、などといったことを確認しましょう。
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回、利用者様の施術に同行しました。
今回の利用者様とは、すごく久し振りにお会いしました。
身の回りの物の位置などに、とてもこだわりをもってみえる利用者様です。
いつもお会いする方ではないため、不慣れなことが多く、何回かイライラさせてしまったかもしれません。
私自身もそうですが、何かにこだわりをもってみえる方は多いのではないでしょうか?
施術の様子
仰臥位にて四肢マッサージ、座位にて肩マッサージと下肢マッサージをおこないました。
その後、歩行訓練も行いました。
歩行について
加齢を重ねるにつれ、歩行のスピードは遅くなります。
歩行のスピードが遅くなる原因は、歩幅が小さくなることです。
歩幅を大きくするには、下記のような力を鍛えるトレーニングが必要となります。
1、体を支え、足を大きく蹴りだすための筋力
2、足を大きく前後に開くための柔軟性
3、片足で体を支える時間を長くするためのバランス能力
高齢者になると、上記のような力が低下してしまいます。
訪問マッサージでは、マッサージ・筋力訓練・歩行訓練などをおこなうことで、歩行に大切な力のトレーニングを行うことができます。
歩行に重要なポイント
普段何気なくおこなっている歩行には重要なポイントが3つあります。
この3つのポイントが1つでもかけると正しい姿勢で歩行ができなくなってしまいます。
ポイント1:正しい姿勢
ポイント2:体の捻り
ポイント3:足の動き
膝や腰が曲がった姿勢では足を高く上げることが難しいですし、体のひねりがなければ歩行をしているとすぐ疲れてしまいます。また、つま先を上げ、かかとで着地する動作は転倒を予防することにおいて重要となるのです。
良い姿勢とは?
背筋:目線は前方を真っ直ぐ向き、背筋を伸ばす
腹筋:おなかが潰れないようにする
おしりの筋肉(大臀筋):股関節を真っ直ぐ伸ばす
ふとももの筋肉(大腿四頭筋):膝関節を真っ直ぐ伸ばす
代表的な悪い姿勢
■猫背タイプ
・背筋や大腿四頭筋の筋力低下により、骨盤が後傾し、膝や腰が曲がった姿勢になる
・膝が曲がっているため、足を持ち上げるのに余分な筋力が必要になる
・腰が曲がり、おなかが潰れているため、呼吸がしづらい
■出腹(おなかを突き出している)タイプ
・腹筋の筋力低下により、骨盤が前傾している
・自分では姿勢が良いと思っていることが多い
こんにちは。コーディネーターの片田です。
本日は、利用者様宅での施術に同行しました。
いつも座ったままで横になるのが嫌だと言われ、座位でのマッサージ。
下肢でも下腿部の浮腫が強く、体が華奢なわりにはバランスが悪い位の浮腫です。
浮腫の原因
浮腫の原因と考えられるものとして下記のものが挙げられます。
1、筋力の低下
筋肉は収縮(伸び縮み)することにより、静脈やリンパ管の流れを循環させるポンプの役割をします。特に、ふくらはぎの筋力が低下すると、老廃物を送り出す力が弱くなります。
2、呼吸による腹圧の力の低下
猫背等姿勢が悪くなることにより、1回の呼吸が浅くなます。
そうなるとリンパや静脈を押し上げる力が低下します。
深い胸式呼吸ができると、静脈の循環する力を高めてくれます。
3、骨盤や下肢がゆがんでいる場合
骨盤が歪むと、その周辺と下半身のリンパ管などの体内の循環を悪化させてしまいます。足のむくみは、骨盤の歪みがきつくなるO脚の人に多く起こる傾向があります。
施術の様子
強めのマッサージだと痛がられるので、弱めで念入りにマッサージします。
座位での下肢のマッサージではある程度までしか出来ず、出来たら横になっていただいた方がより良いマッサージを提供できますが、利用者様本人が嫌がられます。
利用者様の性格上、あまりこちらが強く指示すると、性格が浮き出て、閉ざしてしまうので注意が必要ではありますが。
先生もそんな中で優しくコミュニケーション取りながら、横になって貰えるタイミングを伺っている様子です。
1日座っていたら下腿部の浮腫はなかなか改善していかないのではと思います。
足の浮腫の改善方法
1、マッサージで筋肉を和らげる(弱めでも良い)
2、お風呂や足湯などで温める
3、長時間同じ姿勢を取らないように、こまめに体を動かす
※ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれるほど、重要な役割を持っています。ストレッチなどでふくらはぎの筋肉を動かす習慣をつけましょう!
4、ビタミンやミネラルを摂取する