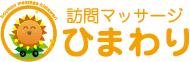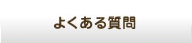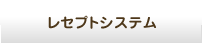お役立ち情報一覧

命に関わる危険な状態のときは、救急車を呼ぶ必要があります。
誰の目から見ても「危険だ!」と判断できる状態であれば、迷うことなく救急車を呼ぶことが出来るでしょう。
しかし、そういった場合ばかりとは限りません。
ちょっといつもと様子が違うな、おかしいなと感じたときはどうすればいいのでしょうか?
そういった救急車を呼んだほうがいいのか判断がつかない状況に遭遇する可能性もあります。
判断が鈍り、そうこうしているうちに、より危険な状態になってしまうこともあります。
そうならない為にも、今回は救急車を呼ぶタイミングについてお話します。
まず、お年寄りの方が倒れた・様子がおかしいと感じたら以下のことをチェックしてください。
①意識があるか
意識がない、意識がもうろうとしている、たたいても反応がない、わけのわからないことをしゃべっている場合は救急車を呼ぶようにしてください。
②呼吸があるか
呼吸をしていない、呼吸が弱い、不規則・おかしな呼吸と感じた場合は救急車を呼んでください。
呼吸は、「目で見る、耳で聞く、皮膚で感じる」の3つを意識してください。
お年寄りの方の顔に、自分の顔の側面を近づけます。
胸部の浮き沈みを目で、呼吸による空気の流れを耳で、呼吸の風を皮膚で感じます。
③脈拍があるか
脈拍がない、脈拍が不規則・おかしいと感じた場合は救急車を呼んでください。
一般的には、頚・肘・手首で脈を感じることができます。
お年寄りの体の状態は変化しやすいものです。
少しでもおかしいと感じたら、主治医の先生に診てもらうこと。緊急の場合は、迷わず救急車を呼ぶようにしてください。

救急の事態の際、第一発見者の処置がとても大切になります。
介護の現場において、救命救急処置を行わなければならないことは稀です。
しかし、いつこのような場面に遭遇するかは誰にもわかりません。
もしもの時のために、救命救急処置の勉強をしておくといいでしょう。
処置について勉強をされる際は、お近くの消防署に問い合わせをしてみましょう。
一般の方を対象として、定期的に講習会が行われていることと思います。
いざというときのために、一度講習を受けることをおすすめします。
いつ何時、救急車を呼ぶ場面に遭遇するかわかりません。
必須事項をまとめて紙に書いておきましょう。
<救急車を呼ぶ手順>
① 電話で「119」
② 救急であることを伝える
③ 「住所」と倒れた方の「氏名」「年齢」を伝える
※家への道順、目印になる建物、家の外見などを伝える。
④ 「いつ何をしているとき」、「どのようにして」倒れたかを伝える。
⑤ 現在の状況を伝える
・意識
・脈拍
・呼吸
・顔色
・外傷の有無
必要になるものをすぐ持ち出せるよう以下のものをまとめて置いておくといいでしょう。
<持っていくもの>
・保険証
・服用している薬、薬の一覧表
・ハンコ
・現金、預金通帳
・筆記用具
・携帯電話
・緊急連絡先
・テレホンカード
救急車が到着したら、救急隊員の指示に従って行動してください。
救急車の中では、
・経過
・本人の持病
・かかりつけ医療機関名
を含め、聞かれた内容について伝えます。
日頃から緊急の際の準備をしておくことが大切です。

急病、事故などにより、お年寄りの方が倒れてしまうことがあるかもしれません。
いつ何時このような状況に直面する誰にもかわかりません。
介護者の方は緊急の場合の対処方法をしっかりと知っておきましょう。
<対処の仕方>
①状態の把握
まず、どんな状態なのかを把握することが大切です。
「あわてず」以下のことをチェックしましょう。
<瞬時のチェックポイント>
①意識はあるか
②呼吸はあるか
③脈拍はあるか
④顔色はどうか
⑤痛みやしびれはないか
・意識がしっかりしている場合
主治医の先生に連絡して来てもらう、もしくは、指示を仰いでください。
判断がつかない場合は、救急車を呼びましょう。
②救急車を呼ぶ
下記のような場合は、ただちに救急車を呼んでください。
●意識がない、はっきりしない
●反応がない、にぶい
●脈拍がない、よわい
●呼吸がない、おかしい
●痛みを訴える
救急車を呼ぶ際、現在の状態を説明しましょう。
※意識がない場合の対処
本人を動かしたりしないで、呼びかけ続けてください。
※呼吸がない場合の対処
気道を確保します。
①本人のひたいに手をおき、アゴの先を手で支えます。
②アゴの先を持ち上げ、同時にひたいを下げるようにします。
処置までの時間によって生死や予後もかわります。
早期の対処ができるよう、知っておきましょう。

お年寄りの方は、若いころと比べて免疫力が低下しています。
つまり、感染症にかかりやすい状態であるため、それに対する予防を行っていくことが大切です。
では、どんなことに気をつけていけばいいのでしょうか?
具体的には、以下のことをしっかりと行いましょう。
<感染症対策>
①体を清潔に保つ
全身をはじめ、口腔内や陰部、その他汚れがたまりやすい場所は、定期的に手入れをし、いつも清潔にしておくことが大切です。
②管は清潔に
吸引器などの管を扱う場合は、手洗いをし、また器具は常に清潔な状態にしておくようにしてください。
③介護者の手洗い・うがい
お年寄りと接する介護者が清潔でなければいけませんよね。
こまめな手洗い・うがい、また食品を扱うときは必ず清潔にしましょう。
④お年寄りの方の体調管理
日頃から体調のチェックをしっかりと行うことが大切です。
また、食事による十分な栄養補給、睡眠をとって、抵抗力を保ちましょう。
⑤お医者さんにみてもらう
早期発見であれば、重症化する前に対応できます。
体調に変化がみられた場合は、なるべく早く医師の診察をうけましょう。
季節に関係なく、感染症は起こります。
毎日清潔を心がけ、無意識にこれらのことができるようにまずは意識して取り組んでいきましょう。

誰でも自分の体調がいつもと少し違うなと感じたことがあると思います。
そう、体調は毎日同じではありません。
特に高齢者の方では、ちょっとした変化にも注意が必要になります。
体調の変化にいち早く気がつくためにも、毎日決まった時間の体調チェックを行うようにしましょう。
今回は、呼吸の測り方とポイントについて紹介しますね。
起きているときの呼吸は、規則的に行われています。
しかし、眠っているときの呼吸は、不規則になりがちです。
起きているときも、眠っているときも観察しましょう。
また、眠っているときは、苦しそうでないかを見るようにします。
ただし、アゴを動かす時は、呼吸の妨げになる可能性がありますので注意してくださいね。
★呼吸の測り方・ポイント
①正常回数を知っておく。
正常な呼吸の数は、一分間に14回~20回といわれています。
それよりも少ない、また多い時は注意しましょう。
②胸の上下で測る。
脈の測定が終わったら、脈を測った手はそのままにし、胸が上下する数を数えます。
それが呼吸数になります。
③無呼吸の有無を確認する
不規則な呼吸の場合、呼吸をしていない時間がある可能性がありますのでチェックが必要です。
毎日測定し、健康なときの数値を把握しておくことが大切です。
その数値をもとに、変化が大きい場合、上昇・下降しているときは注意が必要ですよ。

「いつもと違うな?」と気がつくためには、普段の様子をよくみていることが大切。
毎日同じようでも、体調がまったく同じ日はありません。
体調の変化にいち早く気がつくためにも、毎日決まった時間の体調チェックを行うようにしましょう。
今回は、脈の測り方とポイントについて紹介しますね。
★脈の測定方法とポイント
まず、脈を測るときに診てほしいのは以下の3つです。
●数
●リズム・速さ
●強弱
ポイント
①回数の測り方
正常な脈拍数は、1分間に60回から80回と言われています。
脈が規則的・安定しているのであれば、15秒測り、その回数を4倍にして1分間の回数とします。
脈が不規則で不安定な場合は、1分間測るようにしましょう。
②測る部位
脈を測る部位はいくつかあります。測りやすい部位で測りましょう。
<脈のとれる部位>
・頸部
・鼡径部(そけいぶ)
・腕を曲げる部分
・手首
③測る指について
脈は、中指で測るようにします。軽く当てる、おくくらいのイメージで測りましょう。
しっかり測ろうとすると強く押さえがちになりますので注意してください。
毎日測定し、健康なときの数値を把握しておくことが大切です。
その数値をもとに、変化が大きい場合、上昇・下降しているときは注意が必要ですよ。

体調は人それぞれ、毎日多少違ってくるものですよね。
少しの変化にも気がつけるよう日常の観察チェックが大切になります。
自宅で行えるチェックとしては、顔色や動作の他に、「体温・血圧・脈拍・呼吸」などがあります。
これらを毎日同じ時間帯に測ることで体調の変化を早く察知することができます。
今回は、血圧の測り方とポイントを紹介しますね。
★血圧測定のポイント
自動血圧計があれば、自宅でも簡単に血圧測定ができます。
市販されていますので、一つ用意しておくとよいでしょう。
①ベルトのしめつけ具合に注意。
基本的に上腕に直接ベルトを巻きますが、腕が締め付けられる場合、
薄手の衣服ならば上から巻いてもかまいません。
②心臓の高さで測る。
腕が低すぎたり、高すぎないよう注意しましょう。
③リラックスした状態で測る。
測る前に深呼吸をするなど、気持ちを落ち着かせます。
④測定時は安定した状態のときにする。
測定は食事、入浴、運動などの後は避けるようにし、状態が安定しているときに行いましょう。
毎日測定し、健康なときの数値を把握しておくことが大切です。
その数値をもとに、変化が大きい場合、上昇・下降しているときは注意が必要ですよ。

高齢者の方の体調の変化をみる上で、日常の観察チェックが大切になります。
自宅で行えるチェックとしては、顔色や動作の他に、「体温・血圧・脈拍・呼吸」などがあります。
これらを毎日同じ時間帯に測ることで体調の変化を早く察知することができます。
今回は、体温を測りるときのポイントを紹介しますね。
★体温測定のポイント
①体温は定期的に測る。
毎日同じ時間に、定期的に体温を測るようにしましょう。
ただし、ちょっとでも体に変化がみられるようでしたら、すぐに測るようにしてください。
②高齢者の平熱の基準と変化。
若い人と比べて、高齢者の方の平熱は低くくなります。
また、朝よりも夕方の方が少し体温が高くなりますので覚えておきましょう。
朝いつもより1℃以上も高い場合は、発熱と考えてください。
③しっかりと肌に密着させる。
体温計を挟む部分の汗を拭きとり、しっかりと肌に密着させるように挟みましょう。
痩せている人の場合は、体温計の下にタオルを挟みこんで固定するといいです。
④お腹で測る。
体温をお腹で測る方法もあります。脇の下で測りにくい場合は試してみましょう。
⑤いつも同じ部位で測る。
毎日同じ部位で測ることで、日常の変化がわかります。同じ位置で測るようにしてください。
⑥測定は安定した状態のときに。
測定は食事、入浴、運動などの後は避けるようにし、状態が安定しているときに行いましょう。
毎日測定し、健康な時の数値を把握しておくことが大切です。
その数値をもとに、変化が大きい場合、上昇・下降しているときは注意が必要ですよ。
年をとるにつれて、食事の量が減ったり、あまり運動をしなくなる人は多くみえると思います。
また、腸などの消化器系やお腹の筋肉など体の機能低下も加齢によって起こってきますね。
これらのことから、便秘になるお年寄りの方は増えているようです。
「ただの便秘だから、放っておいても大丈夫だろう」と考えてはいませんか?
放っておくと、腸閉塞になったり、食欲減退など様々な弊害が出てきてしまいます。
家族・介護者の方は、良くお年寄りの方を観察し、便秘かどうかをチェックすることが大切です。
便秘のチェック項目
□お腹が張っている。
□食欲がない。食事の量が減る。
□普段より歩き方、姿勢が前かがみになっている。
□イライラとしている。
□吐き気がみられる。
お年寄りの方がトイレに行くことで安心してしまいがちですが、
家族の方・介護者はこういった様子をいつもよく観察するようにし、便秘のサインが無いかをみていくことが重要です。