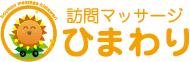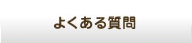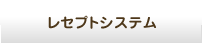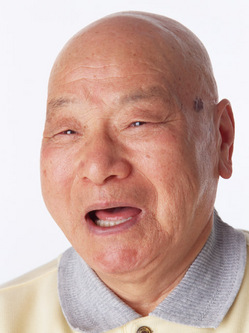お役立ち情報一覧
『なんとも言えない痛みなんだよ』
そうおっしゃってみえた、脳梗塞後遺症のKさん。
右手の麻痺の痛みがどうしようもなくて、毎日眠れない夜を過ごしていたそうです。
そこで、ひまわりの訪問マッサージを試そうと思われたそうです。
危険な4つの痺れ
1、片方の手足がしびれる
脳が原因によるしびれの多くは、体のどちらか片方だけに起きます。まれに両方の手足にしびれが出ることもあります。片方の「手だけ」「足だけ」ということもありますので、油断は禁物です。
2、手袋をはめているような感覚がある
脳梗塞や脳出血によるしびれの特徴として、薄い手袋越しに手足を触っているような感覚の「しびれ」が起きます。正座した後の足のしびれのようにびりびりとした強いものは起きにくいとされています。
3、片方の手と口が同時にしびれる
脳梗塞は梗塞を起こした脳の場所によって体に現れる「しびれ」の場所が変わることが特徴です。手の神経とつながる場所と口の神経についながる場所は比較的近いため、脳梗塞が起こると同時に障害を受ける為、手と口に同時に「しびれ」が出ることが多くあります。
4、 急に起こって数分で消失するしびれや違和感
この症状は「一過性脳虚血発作」で起こります。「一過性脳虚血発作」とは脳梗塞の前兆とも言われます。
突然「しびれ」が現れたと思うと数分後には消えるというのが特徴です。他にも「めまい」「ろれつが回らない」「ものが2重に見える」などの違和感も感じます。
「一過性脳虚血発作」を発症した人の多くは「脳梗塞」を発症すると言われています。なので、この症状が発生したら早めに医療機関を受診する必要があります。
施術の様子
施術内容としては、全身的な軽度のマッサージにより血流改善。
痛み・痺れのある手から肩にかけては入念なマッサージと可動域訓練。
また、痛み・痺れの強い部分には、その日の状態によって治療量を変化させていました。
そのところ「手の嫌な痺れが少なくなった!よく夜眠れるようになった」とお喜びの声をいただきました。
うれしいですね。こういう声が。
むくみ(浮腫)で悩まれているご家族様、ご本人様は少なくないかもしれません。
むくみ(浮腫)は高齢者の多くが訴える症状の一つです。特に、足や手に多くおこります。
だるい・重いなどの不快な状態が続くと高齢者の気分に大きな影響を与えます。また、むくみ(浮腫)よる歩きにくさが出ることから歩行に対する意欲が低下し、寝たきりとなってしまうことも少なくありません。
むくみ(浮腫)とは?
むくみ(浮腫)は血液の循環と深い関係があります。
血液は、動脈から毛細血管を通じて細胞への水分の供給を行います。それと同時に、細胞内で不要になった水分は、静脈やリンパ管に戻って再び体の中をを循環します。
むくみ(浮腫)は、病気などが原因で体の循環機能が低下し、体の中に戻るべき水分が血管外にたまってしまい、水分が過剰になった状態のことをいうのです。
むくみ(浮腫)の原因
むくみ(浮腫)といっても、その原因には様々あります。
●筋力低下
●血行不良
●腎臓、心臓、肝臓の病気
●内分泌の異常
●栄養障害

寝たきりや車椅子での生活など動く機会が少なくなると、上記にもある筋力低下や血行不良によってむくみ(浮腫)が起こりやすくなります。
むくみ(浮腫)は皮膚が引き伸ばされ薄くなり弱くなるため、傷がつきやすくなりますし、褥瘡(床ずれ)の原因にもなります。
そのままにしていると、悪化してしまうことも少なくありません。
そんなむくみですが、血行不良や筋力低下が原因の浮腫みの場合、マッサージや筋力訓練により改善、予防することができます。
ひまわりでは、浮腫の予防、改善を目的としたマッサージも行っております。
むくみでお悩みの方は、一度「訪問マッサージひまわり」にご相談ください。
 「無料体験・お試し」も随時、行っております。 058-234-1386
「無料体験・お試し」も随時、行っております。 058-234-1386
むくみがサインになる病気
むくみに悩む人は特に女性に多いと言われています。
普段であればむくみは危険なものではありません。しかし、むくみの陰に怖い病気が隠れている可能性があります。
1、腎臓病:初期症状はあまり感じられませんが、顔や下肢のむくみが重要なサインになります。
2、心不全:高齢者に多く、もっともむくみやすいのは下肢です。また、下肢のむくみ以外に息苦しさ・胸部の痛みや違和感・息切れ等の症状があらわれます。
3、心臓弁膜症:手足や顔にむくみが起きます。もっとも浮腫みやすいのは下肢です。むくみ以外では息切れ・疲労感・動悸などの症状があります。
4、下肢静脈瘤:特に女性に多い病気です。足の静脈が見た目でも分かるほどにこぶのように浮き出てしまいます。下肢のむくみ・下肢の違和感・だるさ・下肢の皮膚の変色などの症状が現れます。
5、ネフローゼ症候群:代表的な症状としてむくみが挙げられます。特に起こるのは顔のむくみだと言われています。
★自宅でできる簡単セルフケア
ベッドなどで横になるときに足を高く上げるとむくみ(浮腫)の回復を早めてくれます。またむくみ(浮腫)の予防にもなります。
足上げ機能のあるベッドを利用すると簡単ですが、膝から下の部分に座布団などをたたんで敷き、足を乗せるだけでも効果があります。その際は、足先を高く上げる方がより効果的です。
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回は脳梗塞後遺症の利用者様の施術に同行しました。

後遺症は軽かった為、趣味の畑仕事をされていましたが、半年ほど前に畑仕事の際足を滑らせて、5メートルほどある崖から転落されました。
幸い命に別状はありませんでしたが、発見が少し遅れた為、立てなくなり日常生活が1日ほとんど寝たきりになってしまわれました。
ご家族様やケアマネ様も このまま動けなくなるのも大変だと言う事で、訪問マッサージをご利用していただくことになりました。
寝たきりの事実
現在、寝たきりの生活を送っている方は、約100万人だと言われています。
寝たきりの原因は様々あります。病気・怪我などが原因で一度寝込んでしまうと次のような事実が起こるのです。
・1週間寝込むと、筋肉の2割が衰える。
・3週間寝込むと、筋肉の6割が衰える。
・1週間で衰えた筋肉は、1ヶ月のリハビリでやっと改善傾向になる。
これはあまり知られていないですが、事実なのです。
寝たきりにならない為には、健康の維持が大切です。
しかし、どうしても安静にしていなければいけない時もあります。
そんなときに利用したいのが訪問マッサージです。
以前までは脳梗塞の発作が起こった場合、静養第一の考えでリハビリの開始時期が発作から数カ月後ということが多くありました。
しかし、現在では医療技術などの進歩から、リハビリを開始する時期が早ければ早いほど、身体の機能の回復が早いと言われています。
特に、体の状態が良く、意識もはっきりしている場合には、発作後1週間以内にリハビリを開始した方が良いとも言われるほどです。
施術の様子
ご本人様が一番お辛い状況の為、メンタルや体調を見ながらマッサージを進めるようにしております。
関節拘縮予防と筋力強化を図るべく、マッサージとROM訓練を行っています。
最近はご本人様の笑顔を見る事が多くなりました。
現在では端座位保持訓練まで持っていけるようになりました。
他にもこんなお喜びの声が届いています!
ご本人様やご家族様の負担を少しでも軽減出来るように一緒にがんばっていきましょう!
わたし達が全力でサポートいたします!
※写真はイメージです。
日本人が寝たきりになる原因は様々ありますが、もっとも多い原因は「脳血管疾患」であることが分かっています。
他にも、「認知症」、「骨折・転倒」などがあります。
「脳血管疾患」には、脳の血管が破れて起こる「脳出血」「くも膜下出血」、脳の血管が詰まってしまう「脳梗塞」などがあります。

脳は神経細胞の集まりです。部位によって役割が決まっており、ここで血管に異常が起きると今まで司っていた機能が失われてしまうことが多くなります。
体が思うように動かせなくなったり、「寝たきり」になってしまうのはこのためなのです。
「脳血管疾患」は、その部位や再発の危険性などから予後があまり良くない場合があるため、重い後遺症で「寝たきり」になってしまうとご本人はもちろんのこと、ご家族様など周りの人にとってとても大きな負担になります。
そこで「寝たきり」に防ぐためにとても大切なリハビリがあります。それは、「座る」ということです。
「座る」というリハビリを行うとつぎのような効果があるのです。
まず座ることで、身体を支える筋肉を使うため、身体が強くなり、筋肉・関節が固くなるのを防ぎます。

また、寝たきりのためいつも同じ天井ばかりを見ていた単調な生活が、座ることで見える景色が一変し、世界が広がります。
座った姿勢を保てたら、車椅子に乗って外出もできます。
さらに、車椅子に乗れたら、いろんな所に出かけて様々な人との出会いや季節の移り変わりを感じることができ、また寝たきりで食事の時だけベッドを起こしていたときとは違い、他の人と一緒に食事ができます。
そうなれば自然と会話をする機会も多くなり、いろんな人とコミュニケーションをとれて生活が楽しくなります。
ほかにも血圧の調節機能を改善して、起立性低血圧の予防になりますし、体のバランスを改善して、立ったり歩いたりのリハビリにもつながります。
「座る」リハビリを行うことで寝たきりを予防でき、また座ることができれば寝たきりの時よりもずっと多くのことができるようになります。
そうなれば、生きる意欲を取り戻し、表情が生き生きとしてきて、再び人生を楽しむことができるのではないでしょうか。
寝たきりはつくられる
高齢者の方の場合、怪我や病気になると「危ないから・・・」などの理由でつい家族や周囲の人が世話を焼きすぎてしまうことが多くあります。
そうなると、「いろいろ世話をしてもらえるから」と周囲への依存心が強くなり、結果として寝たきりになってしまうのです。
また、過度に安静にしすぎてしまうと、身体機能が低下してしまいます。そうなると、筋力の低下などが原因で寝たきりになってしまいます。
これらを防ぐために、怪我や病気がある程度回復したら、なるべく早く起き上がるようにし、少しでも体を動かすことが大切です。
また、ご家族の方も高齢者が自立して生活を送れるようにするために、世話を焼きすぎず、少し支えるなど自立の支援にとどめましょう。
『訪問マッサージにきてもらってから、歩行が安定してきました。』
そう話をしてくれたのは、Y様の奥様でした。
本日は、右大腿骨頚部骨折が原因で歩行が困難となってしまった利用者様のリハビリ・マッサージ施術に同行しました。

大腿骨頸部骨折は寝たきりになる可能性が高い!
大腿骨頸部骨折は高齢者が寝たきりの原因にもっともなりやすい骨折と言われています。
この骨折の多くは転倒によるものがもっとも多く、骨粗鬆症が骨折を助長させていると言われています。
大腿骨頸部骨折とは?
歩行が困難となりやすい大腿骨頸部骨折ですが、どんな骨折なのでしょうか?
骨粗鬆症によって起こる骨折で多いのは、大腿骨頸部骨折・脊椎圧迫骨折・上腕骨頸部骨折・橈骨遠位端骨折があります。
なかでも、大腿骨頸部骨折がもっとも多く起こりやすいのです。
大腿骨は、足の付け根・股関節付近にあり、体を支える大切な骨です。
大腿骨は常に体を支えているため、転倒や転落の際による力が加わりやすく、骨折しやすいのです。
リハビリの重要性
大腿骨頚部骨折の場合、他の骨折と異なり、ほとんどの場合手術が必要となります。
そのため、できるだけ早期リハビリが重要となります。
手術が必要な理由として、骨折により数日間のベッドでの安静をしているだけでも肺炎などの呼吸器、感染症、褥瘡、認知症などが合併症として起こりやすいからなのです。
また、症状が悪化した場合、生命に危険をもたらす可能性も少なくありません。
施術の様子
3ヶ月ほど、ひまわりのリハビリマッサージを受けていただくようになってから、お身体の状態が調子よく変わってきたようです。
『ひまわりの先生方は、皆心安く話せる』とご家族様よりお喜びの声もいただいています。

Yさま自身も安心して任せていただいている様子です。
先生との会話を楽しみながらマッサージ、リハビリを楽しまれている様子でした。
これからも一緒に頑張っていきましょう!
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回は、腰部圧迫骨折と変形性膝関節症の利用者様の施術に同行しました。
現在ははマッサージ始めて10ヶ月ほどになり、いつも楽しみにマッサージを待っていらっしゃるそうです。 楽しみにしていただきとても嬉しいことですね。
歩行が困難の為寝たきりにならないようにと、ご家族様が切望されました。
腰椎圧迫骨折とは
尻餅をついての転倒や、高所からの落下、交通事故などの衝撃により比較的多く起こる骨折です。
尻餅などの衝撃で腰椎が上下から衝撃を受け、挟まれた腰椎が潰れてしまう骨折です。
リハビリ
骨折直後は痛みなどにより、救急車などで搬送されることが多く、そのまま入院となることがほとんどです。
寝返りや起き上がり時に激痛が走ります。
コルセットを装着することで、つらい痛みが軽減したり、時間がたてば日常生活が支障なくできることができます。
しかし、コルセットを取ると骨折前と同じ動きをしたときに痛みが出るため、不安に思われる方も多くみえます。
「また痛みが出るかも」という不安から「寝て安静にしていれば治る」と思いがちになってしまいます。
それがきっかけで、外出することが減り、自宅でもほとんど寝たきりになってしまいます。
圧迫骨折後に重要なことは、できる限り体を動かすことです。
加齢に伴い、筋肉は硬直しやすくなり、一度固まってしまった筋肉を柔らかく動きやすくするにはとても時間がかかります。
それを防ぐために、訪問マッサージなどでのマッサージやリハビリが重要な役割をするのです。
施術の様子
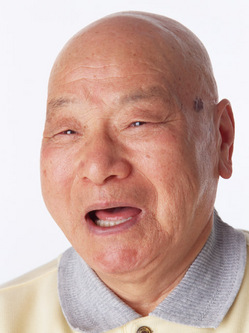 両側臥位、仰臥位にて四肢マッサージ、ROM訓練を行ない、下肢の筋力抵抗運動で筋力の維持・強化を行ないます。
両側臥位、仰臥位にて四肢マッサージ、ROM訓練を行ない、下肢の筋力抵抗運動で筋力の維持・強化を行ないます。
今では、私達が来ると伝い歩きで出迎えて下さるようになりました。
「マッサージをした夜はよく寝れます。食欲も出てきて嬉しい」と利用者様よりお喜びの声をいただきました。
ご家族様にも信頼いただき、「笑顔がふえたんですよ」と喜んでいただいています。
他にもこんな声が届いています!
もっと自由に歩行が出来るように一緒にがんばっていきましょう!
わたし達が全力でサポートいたします!
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回は、骨盤骨折の後遺症で歩行困難となった利用者様の施術に同行しました。
症状
骨盤骨折の症状として骨折部の痛みがあります。この痛みは激痛の場合が多く、少し触られただけでも痛みを感じます。そのため、骨折時には自分に動くことができません。
また、骨盤は内臓を支えているため、交通事故や転落などの強い衝撃が加わった際には、内臓にまで損傷が及ぶことがあります。
内臓が損傷すると併せて、神経や血管も損傷してしまいます。また、腹痛や排泄障害、下肢の感覚麻痺や運動麻痺も起こる場合もあります。
骨折が股関節に及ぶ場合もあり、その場合は股関節に痛みを感じます。
高齢者の場合、骨粗鬆症などで骨がもろくなっていることが多いため、平地で転倒しただけでも、恥骨骨折や坐骨骨折を起こすことも少なくありません。
大きな骨盤の骨折をすると安定性が悪くなるため、しばらくの間、安静と骨盤の固定が必要になります。
安静のために寝たきりでの期間が長くなると、筋力の低下や関節の硬縮が起こりやすくなります。
そのため、できるだけ早い時期からの筋力強化訓練や関節可動域訓練が必要となるのです。
施術の様子

前回お会いした時と比べ驚くほど歩けるようになっていらっしゃり、私も思わず「すごいじゃないですか!」と声を上げてしまいました。
マッサージを受けながら歩くリハビリを一生懸命されていたそうです。
「歩く距離が10数メートルが60m~70mくらい歩けるようになった。」
「下肢の屈伸運動も以前より筋力がついてきた。」
このようなお喜びの声を頂くことができました。
他にもこんな声が届いています!
できなかったことが段々とできるようなるのは、とても嬉しい事ですね。
利用者様の素敵な笑顔を見るたびに私も嬉しくなります。
「まだまだ自分の力で歩きたい!」
このように思われていましたら、一度訪問マッサージを受けてみませんか?。
わたし達が全力でサポートいたします!
脳梗塞の後遺症や、大腿骨頸部骨折などが原因で寝たきりになってしまわれる方が多くみえます。
寝たきりになられた方の中には、膝が曲がり、股関節の拘縮が強く開きにくい方も見えます。
関節は「3週間動かさないと拘縮になる」と言われています。
固くなった関節を元に戻すことは大変です。
そうなる前の予防、また固くなった関節を柔らかくしていくことが大切です
今回は、介護者ができる膝・股関節のリハビリを紹介したいと思います。
★膝、股関節のリハビリ方法
リハビリを受ける本人さんは、仰向けで寝ていただきます。
リハビリは方一方の脚ずつ行います。
① 介護者はリハビリを行う足の外側に座ります。
② 片方の手で膝の裏を支え、もう一方の手で足の裏(かかと)を持ちます。
③ ゆっくりと膝を曲げていきます。足の裏を押して十分に十分に曲げます。
④ 数秒間その状態で止めます。
⑤ ゆっくりと膝を伸ばしていきます。
反対側も同様に行います。
片方10回を目安にしましょう。
★拘縮が強い場合の股関節リハビリ方法
本人様には仰向けに寝ていただきましょう。
介護者は本人様の下肢側に座ります。
※介護者は本人様の両足を揃え、自分の足の間に入れます。
自分の脚で本人様の脚を両側から挟むイメージです。
① 本人様の両膝の間にクッションを挟みます。
② 介護者は、右手を本人様の右膝の内側へ、左手を本人様の左側の内側におきます。
※介護者の手が交差する形になります。
③ 両手で膝を押していき、少しずつ膝を広げていきます。
★注意点
膝を広げる際、扉を開くように手を交差させない開き方をすると、力が入りにくい上、力加減が難しいのでやめましょう。
★ポイント
ゆっくりと時間をかけて行っていくことです。
固くなった関節を動かしますので、ある程度の痛みは伴うこともありますが、痛みが出たら無理をしないようにしましょう。
また、1度にたくさん行うと疲れがでたりしてよくありません。
それよりも短い時間で毎日続けていくことの方が有効です。
拘縮が改善されていけば、日常生活動作もスムーズになり、体全体の運動量が増えてきます。
拘縮のリハビリを行うことで、体全体の機能回復にも効果が出るのです!
リハビリは、本人さんが痛がらない範囲で、ゆっくりと、そして毎日行うことがポイントになります。
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回は脳梗塞で右半身麻痺の利用者様の施術に同行しました。
現在は、ご高齢の為歩行ができず車椅子生活をしてみえます。
マッサージを始める前は座ってるばかりの生活で下肢の浮腫もかなり強かったです。
下肢の浮腫の原因
寝たきりや車いすに乗っている時間が長いと下肢には浮腫が起こります。これは病気でなくても左右の下肢に起こります。
しかし、片方の下肢だけに浮腫が出たり、両下肢に浮腫が出ても左右の下肢の浮腫の程度が違う場合があります。この場合は、何らかの病気を発症している可能性があります。
片方の下肢に浮腫が出る場合は、怪我をしたときに起こる炎症、アレルギー、かぶれなどがあり、さらに脳梗塞後遺症で片麻痺がある方の場合、麻痺のある方の下肢に浮腫が多くみえます。
なぜ片麻痺があると片方の下肢に浮腫が出るのか?
酸素などを多く含む動脈血は、心臓の動きにより全身に運ばれます。
一方、全身をまわり二酸化炭素など老廃物を多く含んだ静脈血は、四肢の筋肉の収縮により心臓に帰ってきます。
しかし、脳梗塞後遺症などで片麻痺がおこると、静脈血を運ぶ機能が十分に働かず滞ってしまうため、麻痺のある下肢に浮腫が起こるようになるのです。
施術の様子

仰臥位にて四肢マッサージ、ROM訓練をおこないます。
両下肢の屈伸抵抗運動など特に右半身は入念にマッサージをおこないました。
固くなってきていた関節も少しずつ柔らかくなり、ご家族様からも「少し楽になって来ました。」とお喜びの声をいただきました。
他にもこんな声が届いています。
これからの時期は寒い日が続くので、お身体が冷えやすい状況ですが、マッサージによって血行が促進されるので利用者様の体調にもいいのです。
お身体がもっと改善されるように一緒にがんばっていきましょう!
わたし達が全力でサポートいたします!
コーディネーターの片田です。
今回は両側の変形性膝関節症の利用者様の施術に同行しました。
施設に入居されている為、施設での施術になります。
訪問マッサージでは、施設へ訪問しての施術もおこなっています。
かなりのご高齢により、歩行がほとんどできず、
車椅子や談話室の椅子に1日座っていらっしゃいます。

寝たきりになるのは、ご本人もご家族様もスタッフ様も望んではいらっしゃいません。
車椅子に座ってお仲間と話したりする事もケアの一つです。
私達マッサージは、関節拘縮や筋力低下の予防に勤めています。マッサージはベッドにて行います。
もちろん、車いすに座ったままでの希望がある場合はそのとおりでも大丈夫です。
いつも寝たきりの状態が長い方の場合は座位をできるだけとってももらっての施術をおこなうこともあります。こちらの方が、リハビリになるからです。
頸部から臀部までの、四肢のマッサージや屈曲抵抗運動、ROM訓練を行います。
膝のリハビリの場合は 膝の痛みが強い場合には関節を動かさないで行う、大腿四頭筋のトレーニングを行ったりします。
これトレーニングはご自身でも行えるようにお伝えしています。
地味な筋力訓練ですが、毎日行うと筋力もつきますし、それ以外の効果もありますので、ぜひおすすめしています。
変形性膝関節症に対するリハビリの目的は、膝の曲げ伸ばしなどの可動性の回復を図る可動域訓練と膝を支える筋力の回復のための筋力訓練です。
この関節の2大機能である可動性と支持性を回復させるリハビりは変形性膝関節症に対するリハビリだけでなく予防法としてもとても重要な役割を持っているのです。
体調をみながらマッサージを変え、常にベストな状態で行っています。
スタッフ様より「マッサージを始めてから談話室まで来ることが増え、笑顔も増えました。」
とお喜びの声をいただきました。
行動することが減り、笑顔もあまり見なくなったとお悩みの方。
一度訪問マッサージを利用してみませんか?
無料体験も随時受け付けております。
もっと笑顔が増えるようわたし達が全力でサポートいたします!
※写真はイメージです。