お役立ち情報一覧
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回は脳梗塞後遺症の利用者様の施術に同行しました。
車椅子中心の生活をしていらっしゃいます。
つかまり立ちはできますが、やや介助が必要な時があります。
デイサービスに出掛けない日の日中はお一人の為、トイレもお一人で行かれますが、トイレで何回か転倒されています。
ご家族様からは転倒しないように下肢の筋力強化を望まれており、マッサージに加え運動療法も取り入れています。
在宅療養の方の転倒の特徴
脳梗塞後遺症の患者さんの場合、運動麻痺・感覚障害などが転倒の大きな原因となります。
また、認知症や意識障害により判断力や注意力が低下して、ご本人が転倒の危険を自覚できない場合もあります。
更に高齢者では、他の病気の合併症があったり、多種類の薬の服用による副作用で、転倒の可能性が高くなります。
転倒の多い場所
転倒される多くの方は屋内で転倒される方が多くみえます。
なかでも、リビング・トイレ・ベッドの周囲が多く、立ち上がる・座る・方向転換などの動作をした際に転倒される場合が多くあります。
転倒される割合では、介助ありで歩ける方は50%、車いすの方は65%を占めています。
トイレで転倒する際にしている動作
トイレで転倒される方の多くが何かをしようと動き始めた時です。
・トイレに腰掛ける
・トイレから立ち上がる
・トイレットペーパーを取ろうとする
施術の様子
端座位から立ち上がりの訓練が一番つらいそうですが、熱心に取り組まれています。
「少しずつですが立ち上がってから静止している時間が長くなってきました。」と利用者様からお喜びの声をいただきました。
もっと楽に立ち上がりができるようになるために一緒にがんばっていきましょう!
わたし達が全力でサポートいたします!
転倒を防ぐには?

転倒を防ぐには、まず身体機能の維持・向上が目標となります。適度に体を動かすことで、筋力低下や関節拘縮を防ぐこともできます。
このようなマッサージやリハビリは医療保険を使ってうけていただけます。そのため、費用が1割負担の方ですと 1回 300円〜500円でうけていただけます。
福祉医療をお持ちの方や生活保護の方は負担はありません。
医療保険を使ってリハビリマッサージを受けるには、医師からの同意書が必要となります。 ご希望の方はいつでもご連絡くださいね。
058−234−1386
※写真はイメージです。
関節の拘縮予防や筋力強化、全身機能の回復を目的としてリハビリを行うことはとても大切です。
起立の基本動作

座位の保持ができないと、立位時にバランスが取れず、起立訓練は危険を伴うため行うことはできません。
座位の保持ができない場合は、まず座位の保持訓練からおこないます。
座位は、意識障害や全身の状態が良好なときから早期に始めると良いとされています。
座位の保持時間は、いきなり長時間は行わず、5分・15分・30分と短時間ごとに行うようにします。最大で30分座位の保持ができるようになったら立ち上がりの訓練を開始します。
立ち上がり訓練
準備:イスやベッドサイドに座り、正面に向かい合うようにイスやテーブルを用意します。
①座った姿勢で、まず両手を体の前で組みます。
②組んだ両手を正面に置いたイスの座面またはテーブルについて、腰をあげます。
※手を組めない人は麻痺のない側の手を座面について腰をあげます。
正面に椅子やテーブルがあることで前方への転倒を防ぐことができます。
椅子やテーブルでなく、介助者が患者さんの正面に立ち、手をとって行うこともできます。この場合は、介助者が引っ張って立ち上がらせるのではなく患者さん自身の力で立ち上がるようにし、あくまでも手をとるだけにとどめます。
この訓練によって足腰、太ももの筋肉を鍛えることができます。
立ち上がり訓練の利点
①下肢に対する筋力強化訓練にもなる
②バランスの訓練も併せて行える
③全身の体力回復訓練にもなる
④歩行や移乗動作に直結しているので、歩行訓練などに進みやすい
⑤失敗がほとんどないため、モチベーションが上がりやすい
⑥介助なくおこなえる。または介助が最小限で済むことが多い
⑦前方で体を支えるため、前方に倒れる恐怖感がなく訓練しやすい
ポイント
一度にたくさん行うよりも毎日少しずつ行うようにしましょう。
リハビリはゆっくりと行い、疲れが残らない程度にするのがポイントです。
準備も簡単で気軽に行うことができるリハビリですので是非実践してみてください。
このような訓練は訪問マッサージでもおこなっています。マッサージと訓練を合わせて行うことで、体にかかる負担を軽減することもできます。
寝たきりや車いすでも生活でお困りの方、一度お気軽にご相談ください。
脳血管障害(脳卒中)とは
脳血管障害(脳卒中)とは、脳の血管がつまったり、血管が破れて出血することによって、脳の組織が障害を受ける病気を総称して、脳血管障害といいます。
また、脳の血管障害が原因で起こる病気を総称して脳卒中といいます。かつては脳溢血(のういっけつ)と呼ばれていました。
脳卒中には、脳の血管が破裂して出血する「出血性」、脳の血管が詰まって発症する「虚血性」の2つのタイプがあります。
出血性では「脳出血」と「くも膜下出血」があり、虚血性では「脳梗塞」があります。
個別の病気としてはどれも皆さんが聞き覚えがある病気だと思いますが、それらを総称した「脳血管障害」という言葉はあまり知られてはいません。
脳血管障害が起きやすくなる危険因子・原因として、高血圧、高脂血症、糖尿病、飲酒、喫煙、肥満、ストレスなどがあげられます。
現在、脳血管障害は、がん(悪性新生物)、心疾患についで日本人の死亡原因第3位になっており、寝たきりの原因としては1番となっています。
高齢化社会や生活習慣病患者の増加により、脳血管障害の患者数は増加しており、それに対する治療や予防が重要となっています。
症状
脳血管障害の症状としては、顔や手足に麻痺が起こったり、言葉が話しづらくなるなどの言語障害、突然の意識喪失、頭痛、めまいなどの症状が起こります。また重症の場合には、死に至ることもあります。
また、症状は病気により異なりますが、一命を取り留めても多くの方に後遺症が残るとされています。
リハビリ
 脳血管障害で残る後遺症に対しては、早期のリハビリテーションがとても重要であり、予後をよくすることがわかっています。
脳血管障害で残る後遺症に対しては、早期のリハビリテーションがとても重要であり、予後をよくすることがわかっています。
生活指導、関節可動域訓練やマッサージなどを行い、ADL(※ADLとは、日常生活動作の略で、起居、移動、食事、更衣、整容、トイレの各動作およびコミュニケーションから成る日常生活に最小限必要と考えられる動作のこと)の向上を目的としてリハビリテーションを行います。
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回は、脳梗塞による麻痺の利用者様の施術に同行しました。
訪問マッサージを受ける前は、いつも寝ている事が多かったらしいのです。
下肢の筋力もかなり低下しており、立ち上がりが困難な状況でした。
高齢者の浮腫の原因
高齢者は、加齢に伴い体を動かす機会が少なくなります。特に病気やけがにより、車いすでの生活や寝たきりという方も少なくありません。
このような状態が続くと、体の機能が衰え、血液を全身に送り出すためのポンプの役割を持っている機能がきちんと働かなくなってしまいます。
さらに、血液の循環に重要な心臓の機能の低下も起こってくるのです。
これらが原因で、心臓から一番離れている下肢に浮腫が起こるのです。
特に高齢者は、筋力の低下も起こりやすいため、下肢を動かすことが困難になってしまいます。
施術の様子
訪問マッサージを受けるようになり、少しずつ足の筋力運動により筋力が改善傾向にあります。
の最後に、先生が横に付き添いながら立ち上がりのトレーニングをします。
トレーニングを続けていくことにより、立ち上がりが早くなられました。

背中が曲がり気味だった姿勢もだいぶ伸びていました。
マッサージとROM訓練
ご家族様がすごく喜んでいただけました。
他にもこんな声がとどいています!
訪問マッサージを始められてから、身体の状態が改善され利用者様やご家族様に喜んでいただけるとわたし達もとても嬉しくなります。
お体の状態を少しでも改善したいと思われていましたら、無料体験も随時実施しているので一度お気軽にご相談ください。
わたし達が全力でサポートいたします!
高齢者の浮腫の危険性
高齢者で下肢に浮腫があるというのは、血液の循環などが悪くなっているということです。
血液の循環が悪いということは、体に起こる症状が下肢の浮腫だけということは少ないのです。
血液の循環の悪さは、臓器の正常な機能の妨げとなり、体全体の不調となることが多いのです。
「ただ足がむくんでいるだけだから・・・」とそのままにしておくのは危険が伴います。
脊髄損傷とは
脊髄損傷とは、脊柱に強い外力が加えられることにより脊椎を損傷し、脊髄に損傷を受けるものをいい、脊髄実質の損傷により、痛み、しびれなどの症状、四肢・体幹の運動障害、膀胱直腸障害などが生じる病態をいいます。
脊髄腫瘍やヘルニアなどの内的原因よっても類似した障害が発生します。
損傷の程度により、完全損傷と不全損傷に分けられます。
<完全損傷>
完全な四肢の麻痺状態になります。多くの場合、骨折や脱臼を伴います。
<不全損傷>
不全損傷は損傷部位によって以下のように分けられます。
①中心性損傷型
脊髄の中心部にある灰白質を損傷することで、上肢の麻痺、手の痛みを呈します。不全損傷で最も多いタイプです。
②半側損傷型(ブラウンセカール)
脊髄の半側を損傷することで、損傷側の運動障害と深部知覚障害、反対側の表在知覚障害を呈します。
③横断性損傷型
脊髄全体が損傷されますが、不全麻痺を呈します。発生傾度は低いです。
症状
上肢の症状としては、上肢の運動障害、筋力低下、巧緻運動障害(細かい指の動きが必要な運動の障害)、知覚障害などの症状を呈します。
完全麻痺では、損傷部の支配する筋肉を動かすことができなくなります。関節周囲の麻痺筋の骨化なども起こります。
下肢の症状としては、歩行障害、歩行不能、知覚障害などが起きます。
さらに失禁、尿閉、便秘といった膀胱直腸障害も起きてきます。また、頸髄や胸髄の損傷では呼吸障害が起こります。他にも、損傷部以下の自律神経障害、それによる消化器障害が起きてきます。
リハビリ
急性期では、合併症の予防を目的としてリハビリテーションを行います。
良肢位保持(枕、タオルなどを使用し筋緊張を和らげます)、褥創の予防、沈下性肺炎の予防のための体位変換、関節拘縮や静脈血栓症の予防のための他動的関節可動域訓練、筋萎縮予防のためのマッサージ、鍼灸治療、肺炎や呼吸機能低下の予防のための呼吸訓練などを行います。
回復期では、寝返り、座位、起立訓練、移動動作訓練、ADL(※ADLとは、日常生活動作の略で、起居、移動、食事、更衣、整容、トイレの各動作およびコミュニケーションから成る日常生活に最小限必要と考えられる動作のこと)訓練、筋萎縮予防のためのマッサージ、鍼灸治療などを行います。
一過性脳虚血発作とは
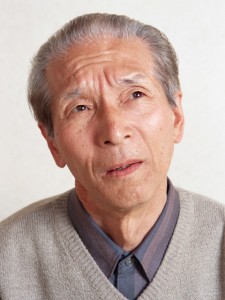
一過性脳虚血発作とは、動脈硬化のある血管にできた血栓がはがれて、脳内の細動脈に一時的に詰まることで血管閉塞や血流減少などの血行障害が起き、それによって起こった脳神経障害で、数分~数時間で症状が改善するものをいいます。
症状が早期に改善するのは、原因となった血栓が溶解されて血行が正常に戻るためです。
一過性脳虚血発作は、脳卒中の一種で、手、足、半身の麻痺やしびれ、軽度の言語障害などを起こします。
危険因子として、高血圧、糖尿病など動脈硬化を起こすものがあります。
症状
症状としては、ふらふらする、まっすぐ歩けない、手、足、半身のしびれ・麻痺、つまずきやすい、手足から突然力がぬける、一時的に片目が見えなくなる、物が二重にみえる、言語障害、めまいなどがあります。
これらの症状は、通常数分~数時間で改善、完全に消失し、元の状態に戻ります。
しかし、一度一過性脳虚血発作により脳の血流が滞ると再び起こりやすくなります。
症状が消失しても放置してはいけない理由
一過性脳虚血発作を発症した場合、そのまま放置すると3か月以内に15~20%の方が脳梗塞を発症するとされています。さらに、その半数は一過性脳虚血発作を起こしてから数日以内(特に48時間以内が危ない)に脳梗塞を発症すると言われています。
これらの症状が出現した場合は、早期に医師の診断を受けましょう。
リハビリ
脳卒中後、リハビリテーション治療でよい成果をあげることができます。
関節拘縮の予防、床ずれ予防、沈下性肺炎の予防のための体位変換、他動的関節可動域訓練、寝返り動作訓練、床上移動訓練、移動・移乗動作訓練、立ち上がりと歩行訓練、応用歩行訓練などADL(※ADLとは、日常生活動作の略で、起居、移動、食事、更衣、整容、トイレの各動作およびコミュニケーションから成る日常生活に最小限必要と考えられる動作のこと)の向上を目的にリハビリテーションを行います。
変形性脊椎症とは
変形性脊椎症とは、脊椎の支持性と可動性が老化のため著しく低下したものをいいます。
椎骨が作る関節が自由に動くのは、関節の表面が弾力性のある軟骨に覆われているためですが、その軟骨は加齢によりすり減り硬くなっていきます。
そのため関節と関節がうまく合わなくなり痛みが生じます。
脊椎と脊椎の間にある椎間板が変性して薄くなったり、変形したりすることで痛みや運動障害を招きます。
もっとも起こりやすい部位としては腰椎で、「腰部変形性脊椎症」と呼ばれます。
症状

椎間板の変形や椎間板に接する椎体の角部分の骨増殖により「骨棘」と呼ばれる出っ張りができます。
この出っ張りが神経を刺激したり圧迫したりすることで痛みが引き起こされますが、必ずしも痛みを伴うとは限りません。
変形が進むと、慢性の疼痛や可動域制限が起こり、神経根症状を生じることも少なくありません。
また、この変形が脊髄や神経が通る道の脊柱管を狭窄させ、「脊柱管狭窄症」を発症させることもあります。
「脊柱管狭窄症」になると、長時間歩くことが困難となります。これは「間歇性跛行」と呼ばれる代表的な症状で、歩行と休息を繰り返します。
安静時には腰痛が出ることは少ないですが、背筋を伸ばして歩いたり立ったりするときに大腿部や膝から下の部分に痛みや痺れが起こり、歩き辛さを感じます。
この症状は座ったり、前かがみの姿勢をとると軽減されます。
他の症状としては、動作の初めの疼痛、重い物を持ち上げることができなくなります。
リハビリ
リハビリとしては保存療法を行います。
症状・痛みの緩和やADL(※ADLとは、日常生活動作の略で、起居、移動、食事、更衣、整容、トイレの各動作およびコミュニケーションから成る日常生活に最小限必要と考えられる動作のこと)の向上を目的として、生活指導、温熱療法、体操療法、マッサージなどを行います。
早期からのリハビリテーションの介入が回復を促進することが科学的に証明されています。
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回はパーキンソン病の利用者様の施術に同行しました。
施設でリハビリと訪問マッサージを併用されています。
いつも私達が訪問すると、ニコニコと手を振って迎えて下さいます。
歩行は介助者と一緒に歩行器で歩いていらっしゃいます。
パーキンソン病と間違えやすい病気
パーキンソン病の初期症状と間違えやすい病気で「本態性振戦」といわれるものがあります。高齢者に多くふるえを主な症状とした病気です。
本態性とは、原因不明ということで、原因がわかりませんが手足、アゴなどがふるえる病気です。
パーキンソン病は何か動作をしようとするとふるえは止まります。しかし、本態性振戦は、逆に動作をするときにふるえが起こります。
例えば、字を書こうとすると手がふるえて書けないというような症状がみられます。
施術の様子
-thumb-250x333.jpg) 両側臥位で頚部から臀部までのマッサージ。仰臥位で四肢マッサージ、ROM訓練をおこないます。
両側臥位で頚部から臀部までのマッサージ。仰臥位で四肢マッサージ、ROM訓練をおこないます。
リハビリで疲れた筋肉をほぐし、関節も柔らかくしていきます。
このままパーキンソン病が更に進行していくのが避けられないなら、進行スピードを少しでも遅くしたい。とのお気持ちでリハビリとマッサージを受けられています。
マッサージを始められた頃より 顔色も良くなり、最近では手先のリハビリにもなる 折り鶴を折りはじめられました。
「マッサージを始めた頃より身体が動かしやすくなって本当に嬉しい。」
このようなお喜びの声をいただきました。
他にもこんな声が届いています!
前向きにリハビリに励まれている利用者様をわたし達が全力でサポートいたします!
※写真はイメージです。
気を付けなければいけない合併症
パーキンソン病ではうつ病の合併症が多いとされています。
不眠や食欲不振、落ち込みや意欲低下などの軽いうつの症状にご家族の方が先に気がつくことも少なくありません。
そのような症状に気づいたときは、医師に相談しましょう。現在は効果的な治療を受けることができます。
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回は外傷性くも膜下出血を患い車椅子生活の利用者様の施術に同行しました。
外傷性くも膜下出血とは?
人の脳には、脳を覆うくも膜という髄膜があります。髄膜の下(くも膜下腔)で出血が起こり、脳脊髄液の中に血液が混ざってしまった状態の事を「くも膜下出血」と言います。
特に、頭部に転倒や交通事故などの外的な衝撃を受けた時に、脳と硬膜を結ぶ血管が切れて起こった状態を「外傷性くも膜下出血」と言います。
症状
激しい頭痛、吐き気や嘔吐、意識障害などの症状が現れます。
「外傷性くも膜下出血」では、その出血量が多いほど症状は増悪します。特に出血量が多い場合には、意識障害や半身麻痺、言語障害といった症状が現れることも少なくありません。
後遺症とリハビリ
「くも膜下出血」は、症状が起きた後のリハビリによって症状の改善が望める疾患です。逆に、リハビリを行わないと症状の悪化を招くこともあります。
くも膜下出血後の後遺症を避けるため、くも膜下出血を発症した患者さんには、安静が必要になってきます。
安静にすることで、脳の出血した箇所の症状を抑えて、患部を安定させるために静養を行います。
しかし、その静養のし過ぎによって生活に必要な機能が低下することが多くあります。
例えば、筋力の低下による筋萎縮や関節が硬くなり動けない関節拘縮、床ずれ(褥瘡)による組織の壊疽が発生いたします
寝たきりで動けないからといって、ベッドでじっと過ごすのではなく、ベッドの上でも体を動かすことが重要となります。
「手足を動かす」、「体の向きを変える」といった動作でも十分なリハビリになります。
施術の様子
お身体を動かす機会が少なく、筋力が低下してきています。そのため、立ち上がる事や背もたれ無しで座る事が困難な状態になっています。

四肢のマッサージと下肢の曲げ伸ばしの関節可動域訓練で筋肉と関節を柔らかく解し、筋力をつける為座位保持訓練もおこないます。
足の曲げ伸ばしの時は少し痛そうですが、いつもニコニコしながらお話してくださります。
その笑顔に私はいつも癒されています。ありがとうございます!
「早く自分の足で動きたい」と、積極的に訓練に励まれています。
楽しくお散歩ができるようになるために一緒に頑張っていきましょう!
わたし達が全力でサポートいたします!
利用者様からはこんなお喜びの声も届いています!
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回は、脳梗塞後遺症とアルツハイマー型認知症による寝たきり状態の利用者様の施術に同行しました。
脳梗塞と脳出血の違い
脳梗塞、脳出血を総称して脳卒中と呼ばれることが多いです。しかし、発症の仕方や症状の出方には大きな違いがあります。
「脳梗塞」は脳の血管の一部が血栓や何らかの原因で詰まり、血流が滞り、その周辺の脳細胞や神経細胞が壊死を起こす病気です。
一方、「脳出血」は脳内の血管が破れて出血を起こし、出血が血腫(血の塊)となって脳の神経を圧迫して機能障害を引き起こしたりして脳細胞へダメージを与える病気です。
脳梗塞のリハビリの目的
脳梗塞など脳卒中全般の治療でもっとも重要なのはリハビリです。
脳梗塞などが原因で一度破壊されてしまった脳細胞や失われてしまった体の機能を復活することは難しいのです。
しかし、人間の脳は失われた体の機能を、他の部位が代行して働くことで、失われた機能をある程度補うことができるのです。
このように、失われた体の機能を再構築するのにリハビリは大きな役割を持っているのです。
マッサージにも大きな役割が!!
訪問マッサージなどで行うマッサージは単に筋肉の緊張を和らげるだけではありません。
麻痺のある部位にマッサージや関節可動域訓練などで体を動かしながら繰り返し体に刺激を送ることで、脳内に感覚を処理をするための回路を新たに作ったり、体を動かすための回路を作らせたりをすることができるのです。
施術の様子

関節の拘縮があり、特に下肢の関節拘縮が強くあります。また寝たきりの為、下肢の浮腫もあります。
仰臥位で四肢のマッサージ、関節可動域訓練をおこないます。
マッサージでは、下肢の浮腫の改善にも効果的なのです。
下肢関節可動域訓練では、利用者様のお身体に負担がかからないよう慎重にじっくりとおこなっています。
ご本人様とはお話はできませんが、ご家族様より「以前と比べて関節が動くようになって、オムツ交換がしやすくなりました。」とお喜びの声をいただきました。
他にもこんな声が届いています。
ご家族様の負担も軽減できるよう、一緒に頑張っていきましょう!
私たちが全力でサポート致します!

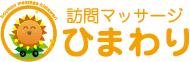



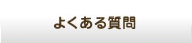
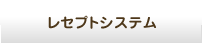



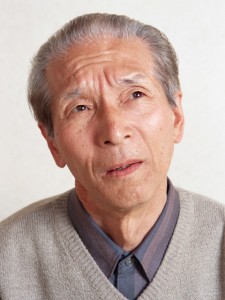

-thumb-250x333.jpg)







