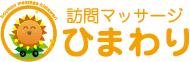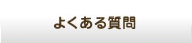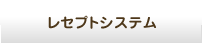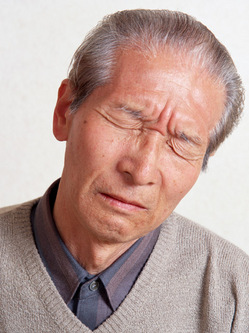お役立ち情報一覧
関節リウマチとは?
関節リウマチとは、関節を主に病変とし、全身の支持組織を多発性におかす慢性の炎症性疾患のことをいいます。 進行すると、関節の破壊や変形が起こります。 女性に多く、20~50代に好発します。
原因
リウマチは「自己免疫疾患」といわれ、かかりやすい体質の人が何らかの原因によってリウマチを発症すると考えられています。 詳しい原因は不明ですが、細菌やウイルスの感染、過労やストレス、喫煙、出産や怪我などをきっかけに発症することがあるとされています。
症状
リウマチには症状が良く出る活動期とそうでない時期があります。活動期には全身に症状が出やすくなります。 微熱、体重減少、貧血、リンパ節の腫れなどのほか、目や口が乾く、息切れ、だるさ、疲れを感じることもあります。 1 関節症状・・・多発性・対称性に関節に炎症が生じます。初期症状には朝に関節がこわばるのが特徴で、進行すると関節痛、腫脹が起こり、さらに関節の破壊、変形、強直へと進行します。症状が悪化するとこわばりなどの時間が長くなります。 2 関節外症状・・皮下結節、肺線維症、間質性肺炎、胸膜炎、強膜炎、血管炎、虹彩毛様体炎、心膜炎、心筋炎など、多彩な症状が起こります。 3 合併症・・・・腎障害、心障害などが起こることがあります。
リハビリ
リハビリはADL(※ADLとは、日常生活動作の略で、起居、移動、食事、更衣、整容、トイレの各動作およびコミュニケーションから成る日常生活に最小限必要と考えられる動作のこと)の向上と変形の予防を目的に行います。  内容として温熱療法、関節可動域訓練、筋力維持と強化訓練を行います。 リウマチのリハビリで効果があるとされている「リウマチ体操」は運動療法の基本で、理学療法とあわせて、毎日行うことが大切です。 運動には、ストレスを解消し免疫力を高め、関節が拘縮するのを予防する効果があります。 無理のない範囲でからだを動かすことが大切です。 早期からのリハビリテーションの介入が回復を促進することが科学的に証明されています。 訪問マッサージでは、リウマチに対する運動療法もおこなっています。 関節リウマチのつらい症状でお困りの方、一度お気軽にご相談ください。
内容として温熱療法、関節可動域訓練、筋力維持と強化訓練を行います。 リウマチのリハビリで効果があるとされている「リウマチ体操」は運動療法の基本で、理学療法とあわせて、毎日行うことが大切です。 運動には、ストレスを解消し免疫力を高め、関節が拘縮するのを予防する効果があります。 無理のない範囲でからだを動かすことが大切です。 早期からのリハビリテーションの介入が回復を促進することが科学的に証明されています。 訪問マッサージでは、リウマチに対する運動療法もおこなっています。 関節リウマチのつらい症状でお困りの方、一度お気軽にご相談ください。
褥瘡とは、一般的に「床ずれ」といわれているものです。
褥瘡の原因
 ・体が痩せてしまい、骨が出っ張っているところがある
・体が痩せてしまい、骨が出っ張っているところがある
・麻痺や拘縮があり、手足の動きが悪く自分で体が動かせない
・しびれや麻痺などがあり感覚が鈍い
・皮膚や筋肉が衰えてしまい、皮膚の弾力がない
・オムツを使用している
・尿失禁・便失禁がある
・栄養が偏っている
上記のようなものなどが褥瘡の原因になるとされています。
これらの原因がいくつも重なり褥瘡となってしまうのです。
特に高齢者の場合、皮膚の弾力が低下しているため、長時間の圧迫やズレに弱く褥瘡になりやすいのです。
褥瘡の好発部位
褥瘡にはできやすい部位があります。長時間とっている姿勢により好発部位は変わってきます。
・仰向きでは、お尻(仙骨部)・踵・後頭部
・横向きでは、肩・腰骨
・座位では、お尻・背中
主な症状
●圧迫されないようにしても赤みがとれない
●水疱ができている
●化膿している
褥瘡は、「つくらない」ことが一番大切です。
体重がかかりやすい場所などに、クッションを使ったりして予防をしていきましょう。
それでも、褥瘡ができてしまったらどう対処すればいいのでしょうか?
まず、クッションなどを使って徐圧をしてもとれない赤みがでてきた場合は、皮膚が破れないように注意し、クッションなどを使用して体重がかからないようにします。
この時点で、一度医師に相談するようにしましょう。
水疱ができている場合は、皮膚が破れないように注意しながら圧迫を避けます。
皮膚が破れなければ、水は自然と体に吸収されます。
注意としては、患部に尿や便などがつかないようにしましょう。
なぜなら、細菌がつくと、繁殖し化膿することがあるからです。
また、血行不良が原因ということから、血行改善を目的として、マッサージをする人もいるようですが、かえって逆効果になる場合がありますので絶対に行わないようにしてください。
「もう少し様子をみよう」とそのままにしたり、自己判断で市販の塗り薬、貼り薬などを使用するのは危険です。
まずは、このような症状がある場合、皮膚の状態が気になるようなら、一度医師や看護師に相談をしてくださいね。
褥瘡ケア、早期発見・治療を心がけましょう。
みなさんの中でも、ほとんどの方が便秘になった経験があるのではないでしょうか?
高齢者の場合、内臓や筋肉の機能低下や、運動量・食事量が少なくなることで特に便秘になりやすいです。 軽く考え放っておくと、腸閉塞や食欲減退など様々な弊害が出てきてしまいます。
そうでなくても、ご本人様も家族の方も便秘になると不安・心配になりますよね。 ご家族・介護者の方は、まずは、便秘にならないための予防をすることが大切です。
便秘を予防する3つの方法
①食事の改善・見直し
●一日3食しっかりと。特に朝!
●水分を摂るように!
●野菜など食物繊維の多いものを!
●牛乳やヨーグルトがおすすめ!
②排便の習慣化
●決まった時間にトイレに! ※便意がなくても
●便意があるときは我慢しないでトイレへ!
③軽い運動
●散歩をしよう!
●お腹のマッサージも効果的!
●寝たきりの方は、左右の体位変換をこまめに!
便秘の予防として、これらは自宅で簡単に行えます。
しかし、こういった予防策をしても便秘が改善されない場合は、一度医師に相談しましょう。
便秘のサインに気が付くポイント!
年齢を重ねるにつれて、食事の量が減ったり、あまり運動をしなくなる人は多くみえます。
また、腸などの消化器系やお腹の筋肉など体の機能低下も加齢によって起こってきますね。 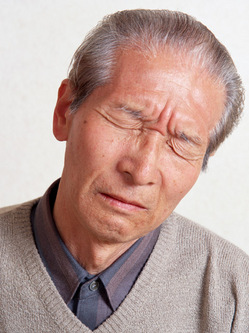
これらのことから、便秘になる高齢者の方が増えているようです。
ご家族・介護者の方は、普段から高齢者の方を観察し、便秘かどうかをチェックすることが大切です。
便秘のチェック項目
□お腹が張っている。
□食欲がない。食事の量が減る
□普段より歩き方、姿勢が前かがみになっている。
□イライラとしている。
□吐き気がみられる。
高齢者の方がトイレに行くことで安心してしまいがちですが、ご家族の方・介護者はこういった様子をいつもよく観察するようにし、便秘のサインが無いかをみていくことが重要です。
脳梗塞後遺症などが原因で寝たきりとなっている方では、便秘となられている方が多くみえます。
便秘による不快感により、リハビリに対する意欲も減退してしまうことも少なくありません。
訪問マッサージにより関節拘縮の改善だけでなく、便秘の解消もできます。
寝たきりによるお体の不調でお困りの方、一度お気軽にご相談ください!
膝の痛みは、加齢によりその症状を訴えられる方が増えていきます。
膝の痛みと言っても、痛みの原因が様々です。
今回は、膝についてのお悩みで多い例をご紹介いたします。
肥満による膝の痛み
太りすぎの患者様の膝の痛みのほとんどは「変形性膝関節症」による痛みが多くあります。
まず、肥満の方で膝の痛みが出た場合、まずこのような質問をします。
・もともと膝が悪かったか
・以前にどんな診断と治療を受けたか
これにより大体の背景が把握できます。
次に膝に腫脹があるか、触診で熱感があるか、左右差があるかなどを調べます。
変形性膝関節症の場合、普段は腫脹や熱感は認められませんが、急性の炎症を起こしている場合は、それらを認めます。
炎症が起きているときは、原則として膝を冷やし、炎症をおさえるようにします。
また、炎症が起きているときは、痛みを我慢できる範囲内でADL(※ADLとは、日常生活動作の略で、起居、移動、食事、更衣、整容、トイレの各動作およびコミュニケーションから成る日常生活に最小限必要と考えられる動作のこと)を行うようにし、無理な運動は避けるように指示します。
痛みは1~2週間で軽減する場合が多いので、炎症が治まってきたら、すぐにADL・関節運動の量を増やしていき、できるだけ早く元の生活にもどすように関節可動域訓練などのリハビリを開始します。
膝の水
よく「膝に水がたまっているから悪い」、「膝に水がたまっていないから良い」と思われている方がお見えですが、医学的には「よい・わるい」というわけではなく、「膝に水かたまる」というのは、あくまでも膝に炎症があるために起こっている一症状にすぎません。
そもそも、膝の水ってなんなんでしょうか?
「膝の水」と言われているのは、骨と骨をスムーズに動かすための役割をしている「関節液」というもののことをいいます。膝には関節包という関節を包む袋のようなものがあり、その中に関節液が入っています。
この関節液自体が痛みの原因にはなりませんが、関節液の量が多くなってくると、関節が張って動かしにくくなります。この時に膝を曲げようとすると、痛みが出てくることがほとんどなのです。
関節を水風船に例えるとわかりやすいかもしれません。
少し水の入った水風船なら、ゴムに余裕があるためある程度なら曲げたり捻ったりしても大丈夫ですね。しかし、限界までに水を入れた水風船はどうでしょうか?
ゴムに余裕がないため、曲げたり捻ったりできませんね。無理に形を変えようとすれば、ゴムが耐え切れず割れてしまいます。

そのようになったときは、整形外科などで膝の水を抜くことがあります。
「一度膝の水を抜くとクセになる」と信じて見える方もお見えですが、そんなことはありませんので安心してください。
まず水がたまるのは膝に炎症が起きているからなのです。
たとえば、
「あなたが風邪を引き、鼻に炎症が起きて鼻水が出たとします。
あなたは、鼻水がでてきたので鼻をかみましたが、鼻水はどんどん出てきました。」
このとき、鼻水をかんだから新しい鼻水がでてきたわけではないですよね?
風邪が治れば、鼻水も治まります。
ようするに「鼻の炎症→膝の炎症 鼻水→膝の水 鼻をかむ→水を抜く」ということです。
なので、膝の水を抜いたからといってクセになることはないんです。
「手浴」とは、お湯で手だけを洗うことをいいます。
手浴は手が汚れたときや汗ばんだとき、爪を切る前などに行います。
温かいお湯の中では指の関節も動きやすくなるので、握ったり開いたりすることで手のリハビリにもなりますし、洗いながら揉むことで、マッサージの効果も得られます。
寝たきりの方や、脳梗塞後遺症などによる麻痺や関節拘縮がみえる方に効果的です。
手浴の前の準備
・40℃前後のお湯
・タオル
・ビニールシート
・石鹸
・桶(洗面器)
座った姿勢での手浴の方法
座っての手浴を行う場合には、ベッドにミニテーブルを設置したり、体の横に洗面器を置いたりして洗う方法があります。
手浴を行うときの姿勢ですが、上体を安定させるために座ってもらったときに膝の下に枕などを入れましょう。
寝たままの姿勢での手浴の方法
寝たままの状態で手浴を行うときは、介助を受ける人の体の横に洗面器を置いて洗います。

洗う側の肘の下にはタオルや枕などクッションを置いて手を浮かせるようにします。
お湯が介助を受ける人にとって熱すぎたりぬるすぎる可能性があるので、温度を確かめながらゆっくり入れます。
麻痺のある方は麻痺のない側の手から先にお湯に入れるようにしましょう。
そうすることで利用者様はお湯の温度をチェックすることができます。
洗うときは、汚れや汗たまりやすい指の間、つけ根、手のひらをきれいに洗います。
このとき、指先をもって指を広げると関節を痛めてしまうことがありますので指の根元をから広げるようにして洗うのがポイントです。
また、洗い終わった後は、お湯を変えてすすぎ、タオルで水気を十分に拭き取りましょう。
介助を受ける人の手が乾燥している場合は、手浴の前に蒸しタオルを手に巻いて、その上からビニールをかぶせて手をふやかしておくと、汚れやアカが落ちやすいのでやってみましょう。
麻痺のある方は、手の甲を少し押して手を開いてから汚れや汗のたまりやすい指の間、つけ根をきれいに洗いましょう。
洗い終わった後は、お湯を変えてすすぎ、最後は乾いたタオルで水気を丁寧に拭き取ります。
手浴は、簡単に行うことができますし、リラックス効果が高いので、一日一回行うことをおすすめします。
また、手浴をおこなったあとは関節や筋肉がほぐれるので、リハビリやマッサージ効果がさらに高まります。
移乗動作とは、ベッド、車椅子、自動車、トイレ(便器)など他のものに乗り移る動作のことをいいます。
車椅子使用者が日常生活を営む上で欠かせない動作でもあります。
また、移乗動作を訓練することは、自立を早めることにつながります。
この動作を行うには座位が安定していることが大切です。
※ここでは車椅子からベッドへ移乗する方法について紹介します。
移乗動作の流れ 介助なし
①車椅子をベッドにできるだけ近づけ、次に浅く腰かけ、背すじを伸ばします。
②体を前に傾けて腰を浮かせて立ち上がります(中腰姿勢の状態になります)。
※体を前に傾けたとき、ベッド側(麻痺のない方)の手をベッドにつきます。
③片足ずつ踏み変えるか、両足をつけたままで体を方向転換させ、お尻をベッドの方に向けます。
④おじぎをしながら膝を曲げていきゆっくりと腰を下ろして座ります。
注意する動作 その①
移乗動作の中には、体を方向転換させる動作があります。
方向転換とは、立った姿勢を保ちつつ、体の向きを変える動作です。
この方向転換は難しい動作でもあります。
この方向転換には、
・足を一歩ずつ踏み変える
・両足をついたまま手すりを使って体の向きを変える
などいくつかの方法があるのですが、今紹介した方法はどちらも重心をつま先や片足に乗せます。
このときバランスを崩しやすいので方向転換は難しい動作なのです。
この難しい動作でも、バランスを崩さないように介助者が軽く助けることで安全に移乗が行えるようになります。
注意する動作 その②

移乗動作の中には、ベッドや車椅子などの条件に影響されやすい動作があります。
それは、立ち上がり動作と方向転換の動作です。
立ち上がり動作を行う際、ベッドや車椅子の座る面は高い方が立ち上がりが楽になります。
しかしその反面、移乗先の座る面が高すぎると深く腰掛けることが難しくなるので注意が必要です。
手すりやベッド柵の位置、アームレスト(肘掛け)の形によって立ち上がりや方向転換がしやすくなる場合もあります。
また、車椅子のベッド側にあるアームレストやフットレストが取り外しできるとさらに安全に移乗動作を行うことができるので覚えておきましょう。
脳梗塞後遺症や様々な理由で寝たきりとなられている方の多くは、自分自身の力で体の向きを変えたりできなないため、介助により体を移動をおこなっています。
介助を受ける方の体の向きを変えるといった動作の前に、仰向けのまま横に移動させなけらばならない場合があります。
まず、この移動の場合には、無理に全身を動かそうとすると大変です。また、無理に体を動かすことで介護を受ける方に負担が多くかかってしまいます。
ですから、体を移動する場合は、上半身と下半身に分けて動かすようにしましょう!
その方が、移動がスムーズに行えますし、利用者様の体にかかる負担も少なくて済みます。
上半身の移動の介助
① 介助を受ける方に声をかける
この動作を始める前に本人に「今から横に動かしますね」など声をかけておきましょう。それだけで本人の不安を取り除くことができます。急に体を動かそうとすると不安になり、体が硬直してしまい、移動がスムーズにできなくなります。
② 手で首、肩を支える
片方の腕を介助を受ける人の首の下に差し込み、腕で首を、手で肩を支えます。
③ 移動させる
空いている方の手をベッドにつき、ベッドを押すと同時に、首、肩を支えている手で介助を受ける人の体を軽く持ち上げながら手前(横)に引きます。
部分介助の人では、移動のときに頭を少し動かしてもらうようにすると介助が楽になります。
下半身の移動の介助
① 介助を受ける方の膝を立てる
膝を立ててもらうことで腰を浮かせやすいようにします。自力でできる方には自力で立ててもらいます。
② 腰を支える
片手を腰の下に、もう一方の手を膝の少し上に入れて腰と脚を支えるようにします。
③ 手前に移動させる
両手で支えた下半身を手前に引きます。介助を受ける人が重い方の場合は、ベッドに膝を刺させている側の足をのせ、腰を支えている側の足をベッドの側面に当てて引くと少ない力で手前に引くことができます。
ある程度自力でできる人では、できるところは自力で動かしてもらうようにすると介助が楽になります。
こんにちは。コーディネータの片田です。
今回は脳梗塞後遺症による麻痺の利用者様の施術に同行しました。
岐阜市内の利用者さまです。訪問介護のヘルパーさんからの紹介でひまわりのことを知ったとのこと。

こちらの患者様は
マッサージを開始した時、すでに下肢の拘縮が始まっていました。
そして、ご家族の方も
「下肢でも股関節の拘縮が見られ、このままだとオムツも変えられなくなってしまいます。」
「ひどいときだと、痛みがひどいため、介護のさいどならてしまうんですよ〜」
とご家族様のお声もありました。利用者さんも家族さんもとてもお困りの様子でした。
「拘縮進行をできるだけおくらせたいんです。」と「座って食事をさせたい。誤嚥を防ぎたい」『おむつ交換時の痛みをもう少しやわらげたい。』
というご家族様の気持ちと、ご本人様の気持ちをなんとかしたいという思いからマッサージを行っています。
四肢のマッサージからはじまり、しっかりと筋肉をほぐした後に
下肢を中心にROM訓練や伸展筋力抵抗運動。こちらは本人さんの努力も必要です。声かけをしながら、頑張ってもらっていました。
また、足背の浮腫も見られるため、
リンパマッサージ、ストレッチを行っています。 浮腫は下肢を動かさない事からおきるので、足の筋肉をしっかりと動かしてあげて、たまったリンパをもとにもどしてあげる必要があります。
「少しずつではありますが、座れる時間が長くなってきました。」とお喜びの声をいただきました。
『おむつ交換してもらうときの痛みが楽になった!』
拘縮の予防には、ご家族さまにお伝えしましたが、ポジショニングも大事のようです。 先生が寝ているときの手の位置、下肢の枕の置き方などを丁寧に説明されていました。
リハビリも、介護のほうもご家族とご本人さまと協力しながら、今後も関節の拘縮を予防し、楽しい日常生活がおこなえるよう一緒にがんばっていきましょう!
わたし達が全力でサポートしていきます!
これからもよろしくお願い致します。
ポジショニングのポイント
自分で身体を動かせない方は、ゆがんだ姿勢のままでで過ごしていることが多くなります。身体がゆがんだままポジショニングをしてしまうと、変形を助長してしまうことも少なくありません。ポジショニングを行う前は、必ず骨盤が真っ直ぐな位置にあるか確認しましょう。
骨盤が真っ直ぐになっているかの確認は、腰骨が前に一番出っ張っている場所(上前腸骨棘)に手を当てながら、左右のねじれや傾きがないか確認します。
下肢の硬縮
仰臥位(仰向け)で過ごす時間が長くなると足の拘縮になる可能性が高くなります。。拘縮を防ぐためには、早期にポジショニングやリハビリを開始することが大切ですが、すでに拘縮がみられる場合もそれ以上の拘縮が悪化しないように、ポジショニングを行う必要があります。特に仰臥位(仰向け)が長いと尖足位で拘縮してしまうことが多くあります。尖足は、車椅子座位や歩行の妨げになってしまいます。
拘縮した足は、内側または外側に傾いてしまいます。それにより、骨盤のゆがみや背骨のねじれが起こってしまいます。
1つのクッションを両膝の下だけに入れてしまうと、両膝部分しか支えられず、寝返りなどがとりづらく、踵にかかる圧力も軽減されません。
クッションを使う場合は、太ももは外側から、膝下は内側から体を支えます。足の過度な外転・内転を防ぎ、足の動きも確保できます。
●歩行がスムーズにいかない ●ふらついたりと不安定にしか立てない ●長く座っていられない こんな悩みを持ってみえる本人様、ご家族様は少なくないのではないでしょうか? リハビリ・マッサージはこうした方々にこそおすすめのサービスです。 訪問マッサージひまわりでは、マッサージだけに限らず筋力強化訓練や起立・歩行動作訓練を自宅で受けていただくことができます。
マッサージやリハビリが保険で受けられます!
あまり知られてはいませんが、訪問マッサージは保険が適用されるのです。(※医師からの同意書が必要となります。) 後期高齢者の1割負担の方でしたら、自己負担額は交通費も含めて300~500円程度の低料金で受けていただく事ができます。 また、福祉医療受給者証をお持ちの方や生活保護を受けられている方でしたら、公費から施術料がまかなわれるため、自己負担金がかかることなく受けていただく事ができます。 「マッサージやリハビリを受けたいけど料金が高い。」と諦めていた方には、とても安心して受けていただく事ができます。
在宅医療マッサージは厚生労働省により法定料金が決められています。
●「マッサージ治療料」
●「変形徒手矯正術料」
●「往療料」
ご利用者様のご要望・条件により1回あたりの法定利用料が決定されます。
「マッサージ治療料」
<1部位 275円> 通常のマッサージ治療です。
5部位が対象。(右上肢、左上肢、体幹部、右下肢、左下肢)
「変形徒手矯正術料」
<1部位 565円> 関節の可動域訓練です。マッサージ治療も含みます。
4部位が対象。(右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)
※部位について 具体的には、「右上肢(右腕)」「右下肢(右足)」「左上肢(左腕)」「左下肢(左足)」「体幹(体)」のことを言います。
「往療料」
厚生労働省保険局の法定計算により、往療計算は直線距離で「治療院」または「直前の患者様」のお宅からの近い方の距離で算定します。
0.1km ~ 2.0km 1.800円
2.1km ~ 4.0km 2.600円
4.1km ~ 6.0km 3.400円
6.1km ~ 16.0km 4.200円
※表記されている金額は、保険割合適応前の金額になります。
施術の様子
 こちらは、マッサージの様子を撮影したものです。 実は、マッサージを受けれている方は、最初座ってマッサージを受けることができませんでした。 しかし、訪問マッサージをご利用になってから、体幹および四肢の筋肉が徐々につき、今では座ることはもちろん、座っている姿勢を保持する時間が延びました。 さらに、今も立ち上がりのふらつき、歩行時の不安定も改善してきています。 本人様からは「本当に体が全体が楽になってるよ」とお喜びの声もいただいております。 訪問マッサージひまわりは、患者様のお身体の状態が少しでもいい方向へ向かいますよう精一杯施術させていただきます。 「リハビリを受けようか悩んでいる・・」「今の状態をなんとかしたい・・」「マッサージってどんなことするの?」という方は、無料体験も随時行っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。 058-234-1386 ●よくあるご質問は→こちら← ●ご利用料金については→こちら←
こちらは、マッサージの様子を撮影したものです。 実は、マッサージを受けれている方は、最初座ってマッサージを受けることができませんでした。 しかし、訪問マッサージをご利用になってから、体幹および四肢の筋肉が徐々につき、今では座ることはもちろん、座っている姿勢を保持する時間が延びました。 さらに、今も立ち上がりのふらつき、歩行時の不安定も改善してきています。 本人様からは「本当に体が全体が楽になってるよ」とお喜びの声もいただいております。 訪問マッサージひまわりは、患者様のお身体の状態が少しでもいい方向へ向かいますよう精一杯施術させていただきます。 「リハビリを受けようか悩んでいる・・」「今の状態をなんとかしたい・・」「マッサージってどんなことするの?」という方は、無料体験も随時行っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。 058-234-1386 ●よくあるご質問は→こちら← ●ご利用料金については→こちら←
こんにちは。コーディネーターの片田です。
今回は、パーキンソン病を患い、寝たきりの時間の多い利用者様の施術に同行しました。
パーキンソン病は進行性の病気で、以前は「いずれは寝たきりになる」と言われていた病気でした。しかし医療の発達した現在では、早期からしっかり治療をすることで症状が進行するのを食い止めることができるのです。
では、なぜ寝たきりになってしまう方が多いのか?
「寝たきり」になってしまう理由とは?
よく転ぶというのが最初に気づかれる特徴です。ほとんどの方は、発症して1年以内に転倒を繰り返すとされています。姿勢が不安定になったり、危険に対する判断能力が低下するため、注意するように言ってももその場になると転倒を繰り返してしまいます。
バランスを崩したときに手で防御するという反応ができないため、顔面や頭部に大ケガをしてしまうことも少なくありません。
歩行は不安定になり、足がすくんでなかなか前に出にくくなったり(すくみ足)、歩行のスピードがだんだん増していき止まれなくなる(突進歩行)といった歩行の異常も出現します。
徐々に動作が取りづらくなり手足の関節が固くなってしまいます。
このような異常が出てくるため、動こうとする意欲がなくなり最終的には寝たきりになってしまうのです。

施術の様子
今回の利用者様は、寝たきりの時間が多いため、四肢の拘縮があり、下肢の筋力低下もみられ、筋肉が張ってしまいます。
両側臥位にて首から腰、四肢のマッサージをおこないます。
マッサージ開始時は、時折顔をしかめる事がありましたが、徐々に穏やかな表情になられました。
筋肉がほぐれてきたところで、仰臥位にてROM訓練と筋力強化訓練をおこないます。
下肢の屈伸運動を左右10回ずつ一生懸命頑張ってみえました。
仕上げに、立位保持訓練をおこないます。
ご家族様から、「前までは立つことなんてできなかったのに、本当によかった。」とお喜びの声をいただえました。
訪問マッサージを始めてから、元気が良くなりお話する機会も増えたともおっしゃられていました。
利用者様だけでなく、ご家族様の喜んでいただけている表情を見ると私たちまで嬉しくなりますね!
他にもこんなお喜びの声がとどいています!
今後も、ご自分の力で立ち上がれるようになるために、一緒に頑張っていきましょう!
私たちが全力でサポートいたします!
自宅で簡単にできる運動療法
パーキンソン病は、体の動きが次第に不自由になっていく疾患です。毎日寝ていたり、座っていて何もせずに過ごしていると、体の機能はどんどん衰えてしまいます。
毎日少しずつでも体を動かしていくことがパーキンソン病を改善する第一歩となります。
自宅で簡単にできる運動療法で体の機能を改善してきましょう!
また最近の研究では、同じ運動を行った場合でも、音楽に合わせて運動するほうがより効果が得られると発表されています。
運動療法を行う際は、積極的に音楽を取り入れてみるといいですね。
★胸の運動
パーキンソン病では「前かがみの姿勢」になる特有の症状があります。この胸の運動で姿勢を改善していきましょう。
1、深呼吸をして、体をリラックスさせます。
2、息を吸いながら両手を広げ胸を大きく広げます。同時に背筋を伸ばしていきます。
3、「ハアー」と声を出しながら息を吐きます。
★肩の運動
腕回しを行い、肩関節周りの柔軟性を高めて動かしやすくします。
1、気を付けの姿勢から腕を大きく回します。(前まわし、後ろ回しと交互におこないます。)
2、肩をすくめるように、肩だけを上下に動かします。
注目されるマッサージ治療
マッサージなどの治療がパーキンソン病の治療に効果が期待できると注目されています。
パーキンソン病の症状緩和には、適度な関節運動・ストレッチなどのリハビリを行うことが必要となります。日常生活を安定させるためにも持続して行うことが大切ですが、思うように体を動かせない場合が多くあります。
そんな時、専門家によるマッサージ治療が有効なのです。プロの施術では、硬くなってしまった筋肉を和らげたり、関節の動きをスムーズにするなどの効果が期待できます。
しかも、パーキンソン病の治療を目的とした訪問マッサージなどのマッサージ治療は保険適用となります。医師の同意書が必要ですが、経済的負担が軽減されます。
また、介護保険とは異なるので利用限度も気にすることなく利用できます。
 内容として温熱療法、関節可動域訓練、筋力維持と強化訓練を行います。 リウマチのリハビリで効果があるとされている「リウマチ体操」は運動療法の基本で、理学療法とあわせて、毎日行うことが大切です。 運動には、ストレスを解消し免疫力を高め、関節が拘縮するのを予防する効果があります。 無理のない範囲でからだを動かすことが大切です。 早期からのリハビリテーションの介入が回復を促進することが科学的に証明されています。 訪問マッサージでは、リウマチに対する運動療法もおこなっています。 関節リウマチのつらい症状でお困りの方、一度お気軽にご相談ください。
内容として温熱療法、関節可動域訓練、筋力維持と強化訓練を行います。 リウマチのリハビリで効果があるとされている「リウマチ体操」は運動療法の基本で、理学療法とあわせて、毎日行うことが大切です。 運動には、ストレスを解消し免疫力を高め、関節が拘縮するのを予防する効果があります。 無理のない範囲でからだを動かすことが大切です。 早期からのリハビリテーションの介入が回復を促進することが科学的に証明されています。 訪問マッサージでは、リウマチに対する運動療法もおこなっています。 関節リウマチのつらい症状でお困りの方、一度お気軽にご相談ください。